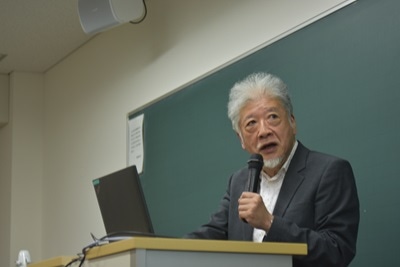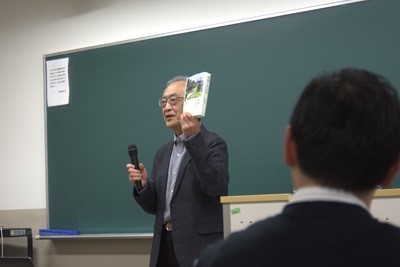2025.03.12.
荻野昌弘・社会学部社会学科教授『破壊の社会学』出版記念シンポジウムを開催
3月8日、西宮上ケ原キャンパスで荻野昌弘・社会学部社会学科教授による『破壊の社会学-社会の再生のために』(荻野昌弘・社会学部社会学科教授 編著、足立重和・追手門学院大学社会学部教授 編著、山泰幸・人間福祉学部人間科学科教授 編著、関西学院大学出版会)出版記念シンポジウムを開催しました。
当日は学内外から約40名の参加者があったほか、中国から方李莉・東南大学芸術人類学・社会学研究所所長らが駆けつけるなど、海外からも多くの方々が参加しました。
シンポジウム冒頭では、足立重和・追手門学院大学社会学部教授による開会あいさつがありました。足立教授は、荻野教授の社会学分野における功績やその視点を解説したほか、今回の書籍タイトルに含まれる「破壊」というキーワードを採用した背景として、荻野教授が扱う資本主義やいじめ、開発などには「破壊」を内包していることなどを紹介しました。
その後、荻野教授による講演「破壊の文学と思想 破壊の社会学基礎論」を行いました。講演では、荻野教授が初代理事長を務めた関西学院大学出版会設立の経緯紹介をはじめとして、自身も愛読する三島由紀夫作品や小津安二郎『東京物語』などを社会学の観点から分析する試み、荻野教授の研究における「追憶の秩序」「博物館学的秩序」の意味などが解説されました。
続く、荻野教授をよく知る好井裕明・摂南大学現代社会学部教授による書評では、「副題には『再生』とあるが、破壊後の社会システムや組織は簡単に再生しても良いのだろうか。また、南海トラフ地震など避けられず予測可能な破壊に対して荻野教授の社会学はどのように考えるか」と鋭い質問が向けられました。この書評に対するリプライおよび討論会の司会は山泰幸・人間福祉学部人間科学科教授が担当。4名による討論会は時間いっぱいまで続き、今回の書籍や荻野教授の社会学に対する理解を会場全体で深めるひと時となりました。
終盤、質疑応答の時間では多くの参加者から質問が寄せられ、シンポジウムは盛況のうちに終了しました。