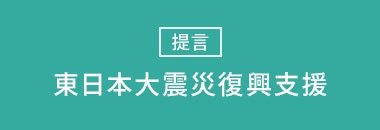災害復興制度研究所は、2005年1月17日、阪神淡路大震災からちょうど10年の節目に誕生しました。
人文・社会科学を中心にした「復興」制度の研究に焦点を合わせる点では全国唯一の研究所です。
Information 最新情報
-
2026.02.20[ニュース]
-
2026.01.14[ニュース]
-
2025.12.19[ニュース]
-
2025.12.12[ニュース]
-
2026.02.20[シンポジウム]
-
2026.02.18[シンポジウム]
-
2026.02.02[シンポジウム]
-
2026.01.14[シンポジウム]
-
2023.02.10[調査]
-
2022.02.28[調査]
-
2021.12.23[調査]
-
2021.12.23[調査]
-
2017.01.21[定例研究会]
-
2016.03.15[定例研究会]
-
2015.10.08[定例研究会]
-
2015.07.30[定例研究会]
-
2025.04.16[公開研究会]
-
2021.05.14[公開研究会]
-
2015.06.24[公開研究会]
-
2015.04.16[公開研究会]
-
2025.07.16[その他]
-
2025.06.20[その他]
-
2025.06.11[その他]
-
2025.06.03[その他]
-
2025.04.10[紀要]
-
2024.03.31[紀要]
-
2023.01.13[紀要]
-
2021.09.30[紀要]
-
2023.09.01[書籍]
-
2021.04.06[書籍]
-
2016.05.27[書籍]
-
2016.05.18[書籍]
-
2025.07.31[ニュースレター]
-
2025.04.01[ニュースレター]
-
2024.12.01[ニュースレター]
-
2024.07.31[ニュースレター]
研究所概要
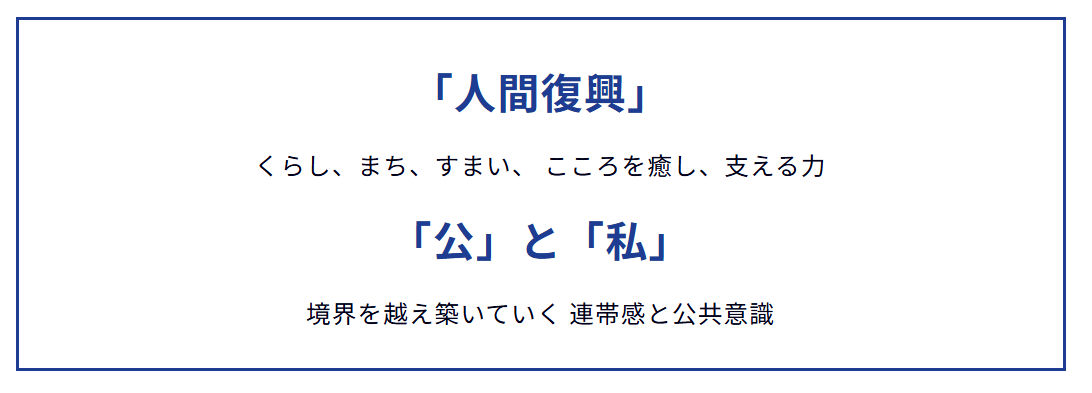
関西学院大学は阪神大震災によって23人の学生・教職員を失いました。激甚被災地・西宮にある大学として、その直後から、学生を中心とした震災救援ボランティア活動や各学部の教員による復旧・復興の研究が行われてきました。
震災から9年が過ぎた2004年1月、学長主導の全学的な試みとして阪神淡路をはじめ全国の自治体・大学・NPOなどの復興支援関係者を一堂に集めた「災害復興制度研究プロジェクト」が開始されました。その結果、関学の強みである人文・社会科学の研究を生かし、よりよい災害復興制度を研究・提案する独立の研究所を新設することになりました。災害復興制度研究所は、2005年1月17日、阪神淡路大震災からちょうど10年の節目に誕生しました。人文・社会科学を中心にした「復興」制度の研究に焦点を合わせる点では全国唯一の研究所です。