[ 文学部 ]ドイツ文学ドイツ語学専修GERMAN LITERATURE AND LINGUISTICS
メッセージ
ドイツ・オーストリア・スイスを中心に広がる〈ドイツ語圏〉。音楽、美術、哲学、文学。科学技術、環境保護、経済大国、移民政策。宗教改革、ハプスブルク帝国、世界大戦の経験。ライン河畔の古城やアルプスの山々、ドナウ河畔の音楽の都……。
様々な知的刺激を与え続けるドイツ語圏の言語・文化・社会・思想・芸術を、現在と過去を往復して学び、中欧からヨーロッパ全体、世界、さらには日本を複眼的に捉え、研究します。みなさんがドイツ語力を伸ばし、学びを深められるように、6人のエキスパート教員がサポートします。
教員紹介
研究キーワードで探す
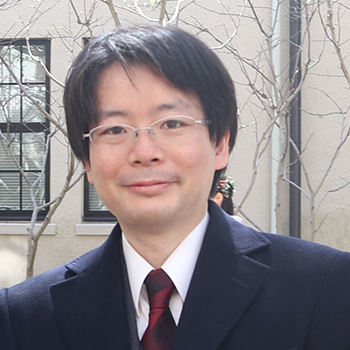
20世紀ドイツの文学・思想・芸術、フランクフルト学派Research keywords
宇和川 雄 教授
20世紀には二つの世界大戦がありました。ドイツは日本と同じく、その二つの戦争の中心にあった国です。この戦間期ドイツの文学と思想が、わたしの主な研究対象です。戦間期のドイツでは、18・19世紀にかたちづくられた近代市民社会の制度と価値観が大きく揺らぎはじめます。
技術革新とインフレーション、そしてナチズムの台頭を前にして、作家や思想家たちも象牙の塔にこもっていたわけではなく、さまざまな応答を試みました。第一次世界大戦から100年を経たいまの時代も、見通しのきかない不透明なものです。当時の批評家の様々な〈問い〉を手がかりにして〈いま〉を考えることが、今後の研究課題です。

ドイツ語学、方言、スイス研究Research keywords
大喜 祐太 准教授
専門はドイツ語学です。歴史的・地域的な変化や社会グループ・使用状況の相違に起因するドイツ語の多様性に着目し、ドイツ語固有の特徴や他の言語との共通点を探しています。また、標準語と諸方言の関係を明らかにするため、ドイツ語圏南部、とりわけスイスで普及しているドイツ語の語彙や用法に注目しながら、スイスのドイツ語と他のドイツ語圏のドイツ語との違いについて研究しています。
言語の研究を通して、スイスという国そのものに魅力を感じています。スイスの多言語教育から「アルプスの少女ハイジ」に至るまで、スイスの文化や社会についての地域研究にも関心があります。

ドイツ・ロマン主義、ドイツ語圏の詩、ドイツ語現代文学Research keywords
水守亜季 准教授
1800年頃に興ったドイツ・ロマン主義は、近代文学の一つの始まりと言えます。初期ロマン主義者たちは、自己反省する自我・主体に重きを置いて先進的な思想と実作で革命をもたらしました。物質的世界のみならず、精神的世界にも目を向ける態度はロマン主義全体に通底していますが、そののちの後期ロマン主義では、自我・主体への信頼に対する懐疑的・批判的な態度を見て取ることができます。
私が研究しているアイヒェンドルフは、後期ロマン主義の中でも特に平易な言葉で素朴かつ敬虔な内容を伝える作者として、ともすると平凡だと低く評価されることもありましたが、その表現の中に実は後期ロマン主義ならではの批判精神が隠されています。ロマン主義研究と並行して、ドイツ語圏の詩、ドイツ語の現代文学、および翻訳にも興味を持ち、取り組んでいます。

ドイツ語学、認知言語学、文法化Research keywords
宮下 博幸 教授
ことばの文法がどのように生まれたのか、また生まれつつあるのかを、特に古ドイツ語ならびに現代ドイツ語のデータに基づいて研究しています。文法が生まれる過程の文法化の際の意味拡張のプロセスに関心を持っています。このプロセスには私たちの世界の把握の仕方や、私たちのコミュニケーションのあり方が密接に関係しています。
文法の成立の研究を通じて、私たちの認知やコミュニケーションの傾向を明らかにするのが大きな目標です。またさらにそのような傾向が、世界のさまざまな言語にどのような形で反映されているのかという点にも関心を持っています。授業ではドイツ語の仕組みについて学ぶ「ドイツ語学概論」や、「ドイツ語史」などを担当します。

グリム兄弟、自然観、18・19世紀の文化Research keywords
村山 功光 教授
多様な思想的・芸術的志向を内包するドイツ・ロマン派を、グリム兄弟を通じて研究しています。彼らは〈本来の人間性〉を問う啓蒙主義の思潮圏内で思考していますが、文学や言語の歴史をたどるうちに、〈人間は固有の民族言語に規定された文化の中で自然に自己形成した〉とも考えるに至りました。
グリム兄弟の創りだした世界には、〈民族的なもの〉を実体化したり〈異文化〉の影響を否定的に捉える危険性もひそんでいます。グリム兄弟の研究を通じて、18世紀後半以降のさまざまな近代批判言説、自然志向の多様な表出、幼年期観の変遷、メールヒェンの可能性などを考えています。
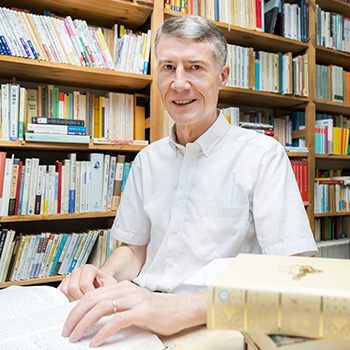
新約聖書学、キリスト教、解釈学Research keywords
Andreas Rusterholz 教授
聖書にはさまざまな人間像が登場し、人間とはどれほど錯綜した存在かがよく分かります。色々な考え方、色々な性格、色々な生き方を生き、環境によって異なる状況に対峙させられています。漫然と聖書を読むだけでは見えてこない多様な問題に対する解決の糸口を、聖書を研究することで掴もうとするのが、私の志す学問です。
学問とは文字どおり“問い学ぶ”ことです。これらの問題を聖書を通して考察し、研究するのが私の仕事です。これは文学にも当てはまります。スイスのドイツ語圏から来た者として、特にドイツ語の文学は興味深い研究対象です。また、ドイツ語から日本語へ、日本語からドイツ語への翻訳や翻訳論などにも興味があります。
授業紹介
- ドイツ語中期留学
- ドイツ語中期留学は、2年生(または3年生)の春学期に約4カ月半、ドイツ・バイエルン州のレーゲンスブルク大学でドイツ語学習を行うプログラムです。プログラムで取得した単位は、文学部の単位として認定されます。
- ドイツ・スタディーツアー
- ドイツの歴史・芸術・音楽・建築・文化・制度等を調べて準備を行い、現地6日間程のベルリンでの調査を通じて異文化への理解を深めます。
平山 栞里 4年生 (撮影当時)
高校生の頃から異文化に興味があり、大学では英語以外の言語に挑戦したいと思いドイツ語を専攻しました。入学後はネイティブの先生の授業などを通じて、たくさんドイツ語を学びました。私は現在夏の短期留学に向けて、協定校であるレーゲンスブルク大学のオンラインコースに参加し、いろいろな国の学生と学んでいます。ドイツ語を学ぶことでドイツ語圏、さらにはヨーロッパの国々が身近に感じられるようになりました。




