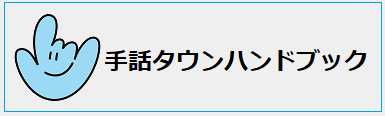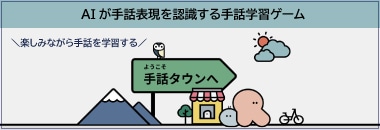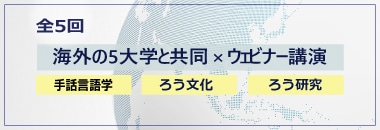研究事業
このページのインデックス
2025年度の研究活動
本研究では、本学人間福祉学部の日本手話受講生を対象に、同授業を通して手話言語を学ぶことで、受講生の文化的多様性のコンピテンス(文化的コンピテンス)が向上したかどうか、またそれが他言語を学んだ場合と比較して何か特徴があるのかを測定することを最終目標にして、文化的コンピテンスの尺度開発を行うことを目的としている。2024年度では文化的コンピテンスに関する文献研究のレビューを行い、文化的コンピテンスには「認識」「知識」「スキル」の三下位概念から構成されているという見解で一致していることを確認した。さらに具体的な測定スケールとして、稲垣亮子(2012、2013)が開発した「多文化間コンピテンス尺度」及び竹井光子(2021)らによる「異文化間能力」スケールについてそれぞれ内容の精査を行った。また個人の異文化への感受性を測定する「異文化感受性発達モデル」(DMIS)にも注目してみた。ただいずれも手話言語教育を念頭に置いたものではなく、下位概念を継承しつつ、具体的なアイテムは新たに創出する必要がある。今年度は、既存研究の成果を踏襲して三下位概念のコンセプトの下で、手話教育に応用できる文化的コンピテンスの尺度化を試みる。まず理論モデルに従い、三下位概念ごとのアイテムプールを作成していく。その上で、Web調査を通してデータを収集、分析するまでに進めることが出来ればと考える。
今西祐介(センター副長 総合政策学部教授)
昨年度に引き続き、本年度も日本手話における統語と談話のインターフェイスに関する研究を継続して行う予定である。特に、日本手話の証拠性(エビデンシャリティー)の研究を中心に行う予定である。日本手話のモダリティー表現を扱った研究であるMatsuoka et al. (2022)の知見を基に、日本手話のエビデンシャリティーの記述と分析を進める予定である。まず、日本手話のエビデンシャリティーが文法形式として存在するのかを検証する。次に、Matsuoka et al.が指摘するように、日本手話のエビデンシャリティーがモダリティーの一部として機能しているのか、あるいはde Haan(1999)やSpeas (2018)等が他の言語の分析を基に主張しているように、両者は別の機能を持つ形式であるのかを検証する予定である。以上と併行して、昨年度に実施した、奄美語喜界島方言のエビデンシャリティーに関する研究を基に、当該言語と日本手話の比較研究も行う予定である。これにより、エビデンシャリティーに関する音声言語と手話言語の比較研究が可能になることが期待される。研究を遂行するにあたり、日本手話母語話者の協力の下、データを収集・分析する予定である。
「梨物語」の語りを用い、日本手話のプロソディ、とりわけ発話末にどのようなプロソディック要素が見られるかを調査する。また、日本手話学習者(手話通訳として活動している聴者)の語りと比較し、プロソディ習得ついて検証する。
2024年度の研究活動として、絵本の手話語りを行ったデータ撮影を行った。2025年度は、これまでのカリキュラムに、ジェスチャーゲームを取り入れたカリキュラム開発を試みる。
日本語において、「ケンは自分の車を洗っている。ハナコも 洗っている。」という空目的語を含む文は「ハナコもケンの車を洗っている」という「厳密な同一解釈」(strict-identity interpretation)と「ハナコもハナコ自身の車を洗っている」という「緩やかな同一解釈」(sloppy-identity interpretation)の両方を許容することが観察されており、後者の解釈は「ハナコも自分の車を洗っている」という文から目的語名詞句である「自分の車を」という名詞句の省略から生じると考えられている(Takahashi 1998など)。一方で、「ケンはカメパンを食べたけど、ハナコはパンを食べなかった」という文は、「ケンはカメパンを食べたけど、ハナコはカメパンを食べなかった」という文とは異なる意味を持つことから、「カメパン」という複合名詞の一部である「カメ」の部分を省略することはできないという制約が存在することがわかる。本研究では、日本語を母語とする幼児が「複合名詞の一部を省略することはできない」という制約の知識をすでに持っているかどうかを明らかにするための調査を実施する。それにより、日本語における省略現象の獲得に関して新たなデータを提示することを目的とする。
本研究では、日本手話話者同士の相互行為の分析を行い、音声言語による相互行為との比較を通して、日本手話が相互行為の資源としてどのように用いられているのかを会話分析の手法を用いて明らかにすることを目指す。昨年度に引き続き、千葉大学の堀内靖雄准教授とともに研究を行い、堀内准教授が所有しているろう者の二者会話のデータを対象とし、特に、日本手話における円滑な順番交替を達成するのに用いられているマルチモーダルな資源について明らかにし、音声言語(日本語)との比較を行った上で、手話言語の話者交替の秩序を解明する。
引き続き、日本手話の空要素の解釈を検証する。日本手話母語話者およびL2日本手話学習者を対象とした昨年の実験結果、ならびに、項削除に関係する新たな言語学的知見をふまえ、実験アイテムを再考し、予備実験を実施する。最近では、項削除が可能な要素(主語、目的語、補文節)は、長距離かき混ぜが可能な要素に限られることがFujiwara (2022)で提案されている。この提案をふまえると、L2日本手話において空要素を項削除と解釈しないL2学習者は、その空要素の長距離かき混ぜの文を容認しないという予測がたてられる。反対に、項削除の解釈をする学習者は、削除された要素の長距離かき混ぜの文を容認するという予測が立てられる。日本手話の項削除、長距離かき混ぜ、話題化に関する先行研究を進めつつ、日本手話での表出の仕方および実験方法を慎重に検討し、予備実験に向けて準備を進めていきたい。
本研究は、天草諸島を中心とした西九州における手話言語のデータベース作成を行うものである。天草諸島は、かつて天草聾学校が存在し、多くのろう者が生活をしていた。しかし、天草聾学校の廃校や地域の過疎化に伴い、島在住のろう者も減少傾向にある。天草諸島をはじめとする西九州は、戦後中国大陸からの引き揚げ者も多くおり、使用されている手話も中国や韓国で使用されていたものとの関連性が見い出される。そのため、現在使用されている標準的な手話とは異なる独特の手話がみられる。しかしながら、高齢化やメディア等による標準的な手話の影響から、かつて使用されていた手話は、消滅しつつある。天草諸島を中心とした西九州における手話を保存し、後世へと残すことは、消えゆく言語の記録であり、手話の歴史言語学等の貴重な資料となる。それとともに、収録した手話データベースを地域に還元することは、その地域で生活をしているろう者にとって自身の言語ルーツをたどることにより、アイデンティティーの形成にもプラスの効果をもたらすと考えられる。筆者は、これまで天草諸島を数回訪問し、手話収録を進めてきた。今年度も引き続き、天草諸島やそこに隣接する長崎、鹿児島地方の手話のデータベース化を目指す。
2024年度研究では、コーダに共通する経験・抱く感情に関する調査の結果をまとめた。具体的には、30名のコーダを対象としたアンケート調査の回答を分析することで、コーダが経験してきた出来事、また、そこで感じたこと、考えたことなどの具体例から、コーダの心理面についての理解を深めることをめざした。その結果、コーダたちの多くが、外で手話を使うことによって注目を浴びた経験、コーダだから手話ができるはずという周囲からの期待を感じた経験をもつことがわかった。なかには外で手話を使うことを恥ずかしいと感じるもの、手話ができるはずという期待に対してプレッシャーを感じるものもいた。結果の後半では、周囲からコーダだと指摘された事柄には表情や視線に関するものが多いなど、コーダの行動様式の共通性についても取り上げた。最後に、ろう親に対するコーダの感情の具体例を多くの記述から示し、そこに見られる社会側の課題についても考察した。2025年度は、コーダの中でも片親が聴者のケースについて実態把握を進めることとする。アンケートはすでに実施しているので、その分析に時間をかける。
ろう者はろう学校の国語で日本語の複合語の読み方を指導されているが、日本手話話者が日本語とは異なるマウジングを使うことが報告されている(Dale-Hench and Yano 2023)。ろう者の日本語の読み方のパターンが明らかになれば、日本手話を第一言語とするろう児に向けての日本語教育に役に立つと考えられる。しかし、先行研究のデータが限られているため、本研究では、日本手話のネイティブサイナーが、複数の発音を持つ単語のマウジングをどのように使われているか調査する。
科研費採択状況
| 代表者 | 研究課題 | 研究種目 | 研究期間(年度) |
|---|---|---|---|
| 平 英司 | 日本語と日本手話のバイリンガル児の言語使用に関する質的調査 | 基盤研究(C) | 2020~2025 |
| 前川 和美 | 難聴児の手話療育体制整備に関する研究 | 厚生労働科学研究費補助金 | 2023~ |
過去の研究活動/科研費採択状況
2024年度の研究活動 関連ページへのリンク 2023年度の研究活動 関連ページへのリンク 2022年度の研究活動 関連ページへのリンク 2021年度の研究活動関連ページへのリンク 2020年度の研究活動関連ページへのリンク
国際連携事業
「プロジェクト手話」は、香港中文大学「手話言語学・ろう者学研究センター」、日本財団、Google、本センターによる共同プロジェクトです。パソコンやスマートフォンのカメラを用いて、手話による自然な会話を認識し、音声言語に変換できる自動翻訳モデルの開発を目指しています。2021年9月に第一弾となる「手話タウン」をリリースし、2023年9月には第二弾となる「手話タウンハンドブック」をリリースしました(現在も継続して内容を更新中)。今後、手話辞書の作成を経て、自動翻訳モデルの開発を目指します。
MORE手話タウンハンドブックについて
●本センターが開発に協力した、手話の学習および手話の検索ができる学習アプリ
「食べ物」「感情」など、シーン別に収録されている手話単語を動画を見ながら練習したり、日本語から手話を、反対に手話に対応する日本語の意味をAI機能を使って両方から検索することができます。現在も更新中で今後さらに語彙を増やしていきます。
MORE
手話タウンついて
●本センターが開発に協力した、AIが手話表現を認識する手話学習ゲーム
ゲーム内では、手話が公用語の架空の町を舞台に、カメラに向かって実際に手話でアイテムを指示しながら、様々なシチュエーションに沿った手話をゲーム感覚で学ぶことができます。また、手話に触れたことがない人から日常的に手話を使う人まで幅広く対象とされています。
MORE
手話言語学、ろう文化、ろう研究等に関する講演動画(全5回)
手話言語学の社会的認知と理解を進めることを目的に、手話を研究しているアジア諸国の5つの大学と連携し、手話言語学、ろう文化、ろう研究等に関する講演動画を配信しています。
日本手話、日本語字幕が付いています。ぜひご覧ください。
MORE
「手話言語学講座(全18講座)」日本手話および日本語への翻訳
香港中文大学を中心に作成された「手話言語学講座(全18講座)」の日本手話および日本語版が完成しました。 「言語学とは?」というイントロダクションから、音韻論・形態論・統語論・CLと、音声言語との比較や手話言語ならではの特性を言語学的側面から丁寧に解説しています。ぜひご覧ください。
MORE