[ 社会学部 教員インタビュー ]貴戸 理恵 教授
“わたし”を研究してみよう
社会学とは、日頃感じる「なぜ」や「どうして」を研究できる身近な学問です。そのため、自分の経験が研究を始めるきっかけになった先生方も大勢いらっしゃいます。
今回は、「不登校」や「生きづらさ」をキーワードに研究されている貴戸理恵教授にお話をうかがいました。

自分を研究するフェミニズムとの出会い
—— 大学時代はどのような学生だったんですか。
大学では社会学部ではなく、総合政策学部に在籍していました。当時はまだ四文字の学部は珍しくて、おもしろそうだと思ったからです。
ゼミが始まっていない大学1~2年のころは、一般教養と語学と情報処理の授業だけで、やりたいことはまだ見えていませんでした。「何かやりたい」という希望は持っていたんですけどね。他のキャンパスに行ってみたくて、メディアコミュニケーション研究所に入ったりもしましたが、「これは違うな」と思って2ヶ月でやめたり…迷走していました。そんな時期にフェミニズムに出会って衝撃を受けたんです。
—— 「フェミニズム」というと、女性を男性と同等の立場にすることを目指す思想のことですよね。社会学の学問分野の一つでもあります。なぜ、そしてどのように影響を受けたのでしょうか。
きっかけは大学の講義を通じて、上野千鶴子さんというフェミニストの『マイノリティの思想としてのフェミニズム』という対談文章を読んだことです。そこで語られていたフェミニズムは、「女性も男性並みにできる」と主張するものではなくて、「この社会において「できる」とはいったい何か?」と問うことで、障がい者など弱い立場にある人びとと連帯していく思想のことでした。「強さ」を目指すのではなく「弱さ」から出発することを大事にする。私の原点です。
また、フェミニズムを通じて学んだのは、「自分を自分で研究しても良いんだ」ということと「そのことが社会を研究するってことと繋がっていくんだ」ということでした。
衝撃を受けた私は、当時別の大学に在籍されていた上野千鶴子さんにお手紙を書いて会いに行ったんです。「私は何をしてあげれば良いですか」と言われたので「ゼミに出席させてください」と言いました。それが大学3年の春のことです。そこから2年間、私はずっと上野ゼミで過ごして卒論を書きました。
「選択は本当にいいこと?」
不登校の在り方に疑問
—— それでは、貴戸先生の研究内容について教えていただけますか。
私の研究の一つは不登校の「その後」についてです。当事者の主体性を重視しつつ社会の構造的な問題について考えていくことが大事だという思いから、このような研究をしています。不登校について少し説明しても良いですか。
—— もちろんです。
1980年代ごろまで、日本社会には、いい学校を出ていい会社に入る、あるいはそういう人と結婚することがいい人生だ、というモデルがありました。そこでは学校に行かなくなるということは「将来まっとうな人生を歩めなくなる」ということを意味していました。そのため、不登校当事者やその親は大いに悩んでいましたし、周りからも非難されていました。当時の文部省(現・文部科学省)は「不登校は子どもの人格や親の育て方の問題である」と言っていましたし、病院の精神科では入院治療が行われていたほどだったんです。
—— 現在とは不登校に対する眼差しがずいぶん異なっていたんですね。驚きました。
そうしたなかで、1980年代の半ばごろから不登校の親の会や民間の居場所ができ、「不登校は子どもの選んだ人生の一つ。不登校でも問題なく社会に出ていける」と主張していきます。これは不登校の権利を擁護するとともに「いい学校+いい会社=いい人生」という社会の価値を問い直していく運動でした。ところが、1990年代以降、若者の進路は多様化・不安定化していきます。そこでは、不登校でも通信制高校やフリースクールで学び進学・就職していく道が開かれるとともに、きちんと学校に通ってもフリーターになってしまうかもしれないような状況が出現してきます。この新たな状況のもとでは、「不登校は一つの選択肢」というかつての運動体の主張は、「不登校を選んでも良い。ただしその結果は自己責任」という新自由主義的な主張に近づいていきます。「選択」という言葉はトリッキーで、社会構造を問えなくさせてしまうんですね。個々の人生として「不登校を選ぶ」ということは言えても、全体を見れば、不登校経験がその後の進学・就職の可能性を狭めることはデータからわかっています。その格差・不平等の実態はきちんと見すえつつ、個々の人生を生きる人のたくましさのようなものも見ていきたい。そんな思いからこの研究をしています。
不登校と経済危機。
きっかけはいつも自分の周りにあった。
—— 貴戸先生が不登校のその後研究をしようと思われたのに、何か直接的な出来事はあったのでしょうか。それについて詳しくお聞かせください。
2つあります。1つは私自身が小学校6年間学校に行かなかった経験があることです。1980年代後半のことで、不登校に対する世間の風当たりはきつく、オルタナティブな学びの場はようやくでき始めたところでした。フリースクールには通っていなかったんですが、不登校・フリースクール運動の言説に救われたことを覚えています。「不登校は人生の選択肢、不登校でも社会に出ていける」という言葉は、当時の私にとっては「あなたはあなたでいていいんだよ」という存在受容の言葉でした。だからこそ、「選択」言説が新自由主義的な「自己責任」に結びついてしまうことに強い危機感があります。
そして2つ目は、2000年代に経験した大学院時代の経済的な不安定さです。私はいわゆるロストジェネレーションとか氷河期世代と言われる、学卒後に安定した雇用に移行できなかった人が多かった世代です。私自身、大学院生時代はさまざまなアルバイトを掛け持ちし、数百万の奨学金の借金を背負い、将来の見通しのない不安のなかで過ごしました。雇用劣化や日本社会の制度疲労など構造的な問題があるのに、「ニートは甘えている」など若者バッシング的な論調が根強かった。社会構造の問題を見ることなく個人の生き方指南をしても、問題は解決しません。「このキャリアは私の選択だからそれでいいのだ」と言っても解決しない問題に出会い、個人の主体性とともに社会構造の制約についてきちんと考える必要性を実感しました。
—— ご自身の経験が現在に繋がっているんですね。この記事は大学進学を考えている高校生の方が読んでくださっていると思うのですが、何かお伝えしたいことはありますか。
大学進学を「就職に有利」「ネームバリューがある」など手段としてとらえている人もいると思います。でも、大学時代は自分が本当に深めたいテーマを深めていける時期。まずは夢中になれるような、「そのことを考えているだけで楽しい!もっと知りたい!」と思えるような自分のテーマに出会って欲しいなと思います。ときには、自分自身の生きづらい経験がテーマを探り寄せる糸になる場合もあります。「これさえなければ生きやすかったのに」と悔やんだ自分の経験が、社会を知るきっかけになることもあるんだよ、とお伝えしたいです。

社会学の面白さは、自分を含む社会を濃密に観察すること
—— ここからは、貴戸先生の研究手法であるフィールドワークについて伺いたいと思います。まずはフィールドワークがどのような研究手法であるか、説明していただけますか。
フィールドワークは実際に現場に行ってインタビューや参与観察を行う質的な研究方法の1つです。自分自身が現場に巻き込まれ、ある程度内側から対象を見るというのがポイントですね。フィールドワークでは、対象者が持つ経験や行為に対する意味づけ、あるいは人や集団が変化していくプロセスを知ることができます。
—— 具体的にはどのようなフィールドワークをされているのですか。
現在、私がフィールドにしているのが「生きづらさからの当事者研究会」という会です。月に1回、「生きづらさを抱えている」と自認する人たちが10~15人ほど集まって話をすることで、自らの生きづらさを共有して深めることを目的としています。私はコーディネーターとして関わっているのですが、日々自分自身が問われます。私にとっては単に研究のフィールドではなく、問いそのものをいただく場としても非常に大事です。
—— 問いをいただくということがフィールドワークならではといった感じがしますね。
そうですね。そもそも、社会学というのは自分が生きている社会そのものを社会の内部にいながら捉えようとする学問だと思っています。その研究方法には様々なものがありますが、私はよくアサガオの観察の例を出します。
—— アサガオの観察ですか。それはどういうことでしょうか。
小学校のときに学校でアサガオの観察をした人は多いですよね。その場合、観察する自分はアサガオから距離を取って、外側から見ています。でも社会学では、観察する人も社会のなかに含まれているから、対象と明確な距離を取ることはできません。自分自身に巻き付いているアサガオを無理やり観察する、みたいな感じですね。特に質的調査では、対象との距離が近くなるので、観察者と観察対象のあいだの切り分けがいっそう難しくなります。揺さぶられるし、不確実性も大きい。でもその複雑さが私にとってはすごい大きな魅力ですね。
フィールドワークでしかたどり着けない事実がある
—— フィールドワークを行う上で、気をつけていらっしゃることはありますか。
まずは、自分の立場を自覚しておくことです。対象との関係性に巻き込まれながら、「ああいま巻き込まれているな」と自分でわかっておくこと。「客観的・中立的」に距離を置いていては見えるものも見えてきません。でも無自覚に巻き込まれてしまうと、現場を混乱させたり、相手に自分の問題を押し付けたりしてしまう。自分の足場を確保しておくことで、失敗はあってもその都度修復しながら関係を続けていくことができます。
それから、こちらのストーリーに相手を当てはめるのではなく、相手に触発されてこちらがもともと持っていたストーリーが変わる、というのを大事にしています。「自分が言いたいことを言うために協力者の発言を利用する」みたいになったら終わりだなと思います。
あとは、当事者言説を大事にしつつそれに引きずられすぎず、研究者としての分析や解釈をきちんと行っていくことですね。
—— 対象者に寄り添いながらも、研究者としてのアイデンティティも大切にしていらっしゃるんですね。
現場には支援者や心理専門家など、直接役に立つことをしている人たちが多くかかわっています。そこに関わる一人として私も混ぜていただくなら、私なりに役に立てることをやっていくしかないですので。

娘が不登校に。
そして気付いた親としての葛藤
—— 貴戸先生にはお子さんがいらっしゃると伺ったのですが、研究者としての不登校に対する考え方と、母親としての不登校に対する考え方は異なるのでしょうか。
とても良い質問ですね。びっくりしました。実は、オーストラリアに住んでいたときに当時5歳の娘が、一時期だけですけど、学校に行かなくなったことがあるんです。そのときは親として、学校に行く・行かないはともかく、この子に元気で幸福でいてほしいと本当に思いました。思えば「不登校は子どもの人生の選択」という主張は、本当に選択肢の一つとして不登校やフリースクールを想定するというよりは、親の立場からの「今はとにかくこの子の在り方を認めよう」という気持ちから出てきた面も大きかったと思うんですね。そういう想像力が働くようになりました。とはいえ、当事者にとっては「選択」と語った不登校の経験を抱えて生きていく「その後」の人生があるわけで、これまでの自分の問題意識を否定するわけではないのですが。
—— 当事者、研究者、そして母親として。様々な立場で不登校を捉えてきた貴戸先生の話を伺うことで、私たち自身も「社会学とは何なのか」ということを再認識できたように思います。本日はありがとうございました。
—— 貴戸教授についてさらに知りたいという方のために、著書をいくつかご紹介します!。
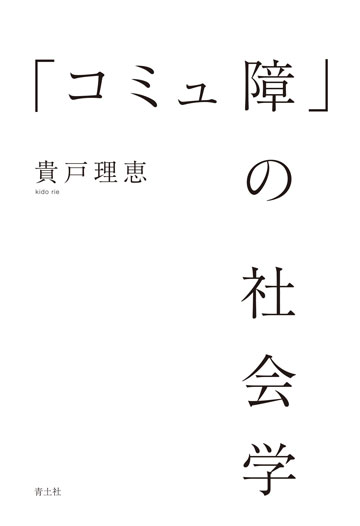
①『「コミュ障」の社会学』
(2018, 青土社)
今回のインタビュー内容の中では、不登校、親としての経験に関することがより詳細に書かれています。
なんとなく生きづらさを抱えているあなたにオススメです。
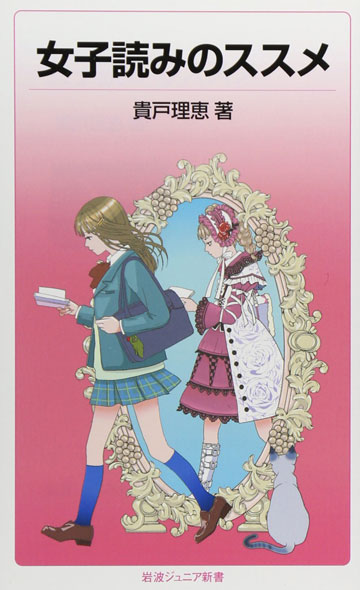
➁ 『女子読みのススメ』
(2013, 岩波書店)
女性が主人公の小説を、女性である貴戸教授の目線で読み解くことで、様々な生きづらさに迫ります。
フェミニズムに関心のあるあなたにオススメです。
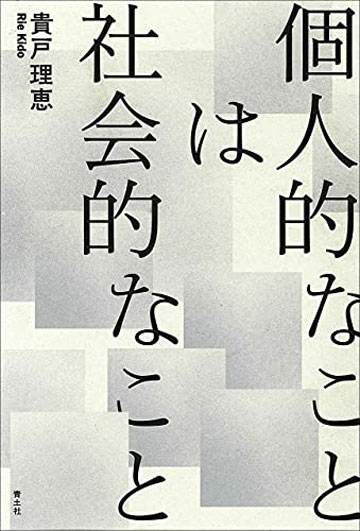
③ 『個人的なことは社会的なこと』
(2021, 青土社)
東京新聞の連載「時代を読む」(2013〜2021)をまとめた一冊。社会問題に関心のあるあなたにオススメです。
記事担当者の感想
- 今回、貴戸先生にインタビューをすることで、いま、やりたいことが見つからなくても、きっと色んな経験をすることでどこかでそれが活きてきて、それが社会学では研究テーマになることもあるのだと思いました。
- 貴戸先生がおっしゃっていたように、大学は自分次第でどこまでもテーマを深めることができる場だと思います。ぜひ関学社会学部の多様な学びから自分の興味関心を見つけ、社会学を楽しんで頂きたいです!
- みなさんにも貴戸先生のように「自分自身のテーマを見つけて」大学生活を楽しんで頂きたいです!
- 漠然と抱えている疑問や不安に対して、光を照らしてくれるのが社会学。入学して以来感じていたことを、今回のインタビューを通して再確認することができました。
- 自分の経験がきっかけに繋がるということに改めて社会学の魅力を感じました。また、フィールドワークで意識している点はとても勉強になりました。

