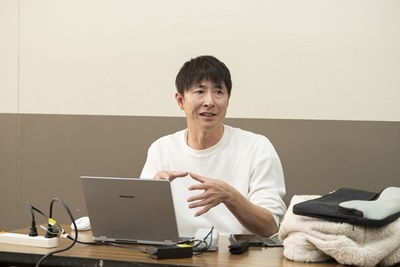[ 法学部 ] 公務に特化した授業公共政策発展演習
政策形成を模擬体験し
ポリシーメモを作成する
この授業は、法学部「特修コース(公務分野)」の科⽬です。公務分野では、公務員として重要な「合意形成能力」「政策企画立案能力」を実践的に養うとともに、幅広い政策分野の「専門的知識」、「公務の思考力」を身に着けることを目的としています。
この授業と応用編の「公務特修実践演習B」(履修基準年度:3年生)では、具体的な政策分野における企画立案(現状分析-課題抽出-政策案の設計等)の一連の過程を経験することで「政策企画立案能力」を涵養します。
授業の特長
- こんな人におすすめ
- ・将来は公務員をめざしており、「政策企画立案能力」を実践的に身につけたい人
・(公務希望でなくても)公共的課題に対する分析力を身につけたい人
- どんな学びや成長ができる?
- ・「公共政策論」などの講義で学ぶ理論(フレーミングや要因分析など)を現実の課題に適用し、分析する力を養うことができます。
・現状分析-課題抽出-政策案の設計という論理的一貫性を大切にしつつ、データや他事例等も活用し、また、必要に応じてその自治体の担当部署にヒアリング調査をさせてもらうことで、単なるアイデアにとどまらない、説得力のある政策案(少し短めのポリシーメモ)を設計できるようになります。
・希望者に対しては、2年秋から受験できる国家公務員総合職教養区分に向けたサポートも別途行っています(授業内容と試験内容をリンクさせた企画提案・政策課題討議の授業、ES添削、模擬面接・アドバイスなど)。
- 授業の雰囲気は?
- グループワークによるメンバー間のディスカッションで政策をつくっていくので、みんな楽しそうに見えました。毎週の課題はとても多いので、大変だとは思います。
- 担当教員が語る他にはない魅力
- 政策をつくってみる、という授業や講座等はよくあると思います。ただ、政策“アイデア”の域を出ないものも多いのではと思います。この授業は、政策立案の実務を実際に担う国家公務員のガイダンスの下、実際の政策プロセスに沿って立案する、という機会を提供します。
理論を背景として、現状分析-課題抽出-政策設計の一連の過程の論理的一貫性を考慮し、ファクトにもとづいて立案することで説得力のある現実に即した政策を立案できる能力を身につけられることが魅力ではないかと感じます。
- キーワード
- 政策形成、政策形成過程、現状分析、課題抽出、仮説検証、事例分析、政策⽴案
- 履修基準年度・担当教員
- 履修基準年度:2年生
- 担当教員(2025年度):小川 大和
授業計画
| 授業計画 | |
|---|---|
| 第1回 |
【オリエンテーション】 【講義】 |
| 第2回 |
【発表】公共政策のデザイン 【アクティビティ】 |
| 第3回 |
【発表】公共政策のデザイン 【アクティビティ】 |
| 第4回 |
【発表】政策分析の8つのステップ 【講義】 |
| 第5回 | 【アクティビティ・グループワーク】 ・2つ目の事例(ポリシーメモ②)について、 -現状分析・課題抽出 -政策案等のアイデア出し(政策事例調査等(比較)) |
|
第6回 |
【アクティビティ・グループワーク】 ・2つ目の事例(ポリシーメモ②)について、 -政策案等を作成 |
| 第7回 | 【アクティビティ・グループワーク】 ・2つ目の事例(ポリシーメモ②)について、 -説明・質疑応答への対応の検討 |
| 第8回 | 【発表】 ・全体の前でグループごとに発表・質疑応答 |
| 第9回 |
【講義】 【アクティビティ・グループワーク】 |
| 第10回 | 【アクティビティ・グループワーク】 ・3つ目の事例(ポリシーメモ③)について、 -現状分析・課題抽出(問・仮説含む)、最終目標まで作成 |
| 第11回 | 【アクティビティ・グループワーク】 ・3つ目の事例(ポリシーメモ③)について、 -政策案、懸念点・対応、評価基準も作成 |
| 第12回 | 【アクティビティ・グループワーク】 ・3つ目の事例(ポリシーメモ③)について、 -ポリシーメモ③(論理性)を落とし込み、政策レポート(10枚程度)を作成 |
| 第13回 | 【アクティビティ・グループワーク】 ・3つ目の事例(ポリシーメモ③)について、 -説明・質疑応答への対応の検討 |
| 第14回 |
【発表】 【議論】 【発表】 |
ここまで読んだあなたへのメッセージ
自分の関心のあるテーマの解決に向けて、解決策を考えてみるというのはとても面白いです。また、それをいかに実現するか、という合意形成(残りの特修コース2授業)とも密接に関連しています。もしよければ、法学部の特修コース公務分野、政策立案のクラスであるこの授業でご一緒させていただければ幸いです。