[ 総合政策学部 ]グローバルキャリアプログラム(GCaP)
グローバルキャリアプログラム(GCaP) ―国際協力コースとは?―

将来、国際機関、国際NGOなどの国際協力、社会貢献活動やグローバルなビジネスの分野で活躍を志す学生に対し、グローバル化に対応した国際競争力のある人材を育成する総合政策学部独自の少人数制プログラムです。その礎となる教養や専門的知識を習得するとともに、さらに関西学院大学が実施する多彩な海外留学や学部で展開している発展途上国へのフィールドワークなどに参加することで実践力や政策応用力を身につけるとともに、高度な実践英語能力やコミュニケーション・スキルを身につけることを目指しています。
※GCaP:Global Career Programの略
GCaPだけの特徴
このプログラムはすべて神戸三田キャンパスで開講されます。本プログラムを担当する教員は、元国際公務員、外交官や、国際ビジネスの現場で、長く海外実務経験を積んだ総合政策学部の教員です。GCaPを履修する学生は、自ら履修授業表を参考に、将来のキャリアパスを意識して、大学2年生からスタディ・プランをたて、卒業まで段階的に、グローバルキャリアを築く上で礎となる知識や教養を身につけ、実践的なスキルや経験を学びます。加えて少人数ゼミでは、実際の国際問題のケースを用いて、課題設定や政策立案の方法を学び、問題解決能力を養うトレーニングを行います。英語によるディスカッションやレポートライティングスキル、プレゼンテーション能力の向上を目指し、より高度な対人関係スキルや多角的な問題思考力を集中的に鍛えることもできます。
実践的なキャリアアドバイスをもらう機会を通して、現実的かつ着実に自身の将来の目標へと進むことができる、それがこのプログラムの大きな特徴です。
本プログラム修了後に想定される就職先・職種
グローバルに展開している国内外の企業、ソーシャル・ビジネス、国連をはじめとする国際機関、JICA、国際NGOなどの国際開発専門職。
現GCaP生の多くが、将来海外の大学院への留学を志望しており、留学に向けての具体的なアドバイスがもらえます。
GCaP指導教員紹介
グローバルに展開している国内外の企業、ソーシャル・ビジネス、国連をはじめとする国際機関、JICA、国際NGOなどの国際開発専門職。
現GCaP生の多くが、将来海外の大学院への留学を志望しており、留学に向けての具体的なアドバイスがもらえます。

小西尚実 教授(国際政策学科)
こんにちは。国際政策学科の小西です。私は、京都大学大学院(経済修士)、英国London School of Economics (労務管理修士)を修了後、外資系企業や国際機関(国連ILO、アジア開発銀行)にて、組織の人事政策や人材戦略に基づく人事管理業務に携わっており、様々な国籍やバックグラウンドの人材の発掘や育成に携わってきました。2009年より総合政策学部教員に着任してから、多くの将来国際公務員やグローバルビジネスに携わりたいという志の高い学生を指導してきました。
GCaPは、このような意欲ある学生達が、自分自身で学習計画や長期的なキャリア設計をたて、その目標を達成するために必要となる実践的な指導を、継続的に受けるチャレンジングなプログラムです。大学生活の4年間は長いようで大変短いです。4年間で視野を広げ自身の可能性を高めて下さい。GCaPで会いましょう!

井上一郎 教授(国際政策学科)
私は、現在大学で中国の政治や外交を研究していますが、今や研究者だけではなく実社会で仕事をするにしてもますます高度で専門的な知識が必要になってきていると感じます。また、日本と世界を隔てる国境が低くなり、当たり前のように英語を使いこなしながら広い視野で仕事をすることが求められています。このプログラムは、グローバルキャリアを目指す意欲的な学生が、豊富な国際経験を持った教員から、勉強だけでなく進路指導も含めて熱心なアドバイスが得られることが特徴です。
【学歴】
関西学院大学法学部卒業(84年)、中国復旦大学留学(87〜89年)、米国タフツ大学フレッチャー法律外交大学院修了(MA,05年、MALD,11年:国際関係論)。
【経歴】
1986年外務省入省後、主に対中国関係を中心とした業務に携わる。その間、在中国日本大使館一等書記官、在広州日本総領事館領事、外務省アジア大洋州局中国課課長補佐などを経つつ、経済協力、政治・経済、外交・安全保障などの業務を担当。09年退職、11年より現職。
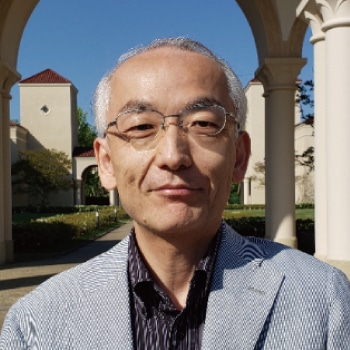
実哲也 教授(国際政策学科)
2019年4月に総合政策学部の教員になりましたが、それまでは日本経済新聞の記者として30数年にわたり、日本の経済政策や国際経済問題を中心に取材し、一般記事や論評記事を書いていました。その間にニューヨーク、ロンドン、ワシントンに合わせて12年あまり駐在し、米国や欧州の経済・政治動向をカバーしました。海外に住んで取材した経験は、世界の問題だけでなく、日本の課題を考えるうえでもとても役だったと感じます。学生時代は4年生のときに初めて欧州ひとり旅をしたぐらいで、海外経験や外国の人々とのつきあいはほとんどありませんでした。自分のこれまでの人生を振り返っても、国際的な舞台で活躍したいと考えている人はなるべく早くからそのための準備を始めた方がいいと思います。総合政策学部のGCapはそれに最適な場を提供するものです。グローバルな視点で物事を深く考える能力や、留学など海外に飛びたつための基礎力を身につけることができるようになるでしょう。
【略歴】
東京大学法学部(政治コース)卒業後、日本経済新聞社に入社。経済部記者としてマクロ経済政策や日米摩擦などを担当。経済金融部長、編集局次長、論説副委員長などを歴任。1980,90年代にニューヨークとロンドンに駐在、ブッシュ政権時の2000年代半ばにワシントン支局長。

清水康子 教授(国際政策学科)
国際政策学科の清水康子です。GCaPは様々な専門の教員と様々な興味を持つ学生の間で刺激を与え合いながら、現代の問題に学際的なアプローチができるプログラムです。私は、難民研究を中心として国際人権・人道支援・国際協力の分野を専門としています。関西学院大学(経済学部)の卒業生でもあり、総合政策研究科ではPhDを取得し、その間にハワイでソーシャルワークを学びました。また、JICAボランティアを経て国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)で25年間難民支援に携わり、その間JICAへ出向するなど、人道と開発の接点である平和構築・移行期支援という広い分野で実務経験をしましたが、その際、学生時代に多分野で勉強したことが国際協力の現場で役立ちました。GCaPで一緒に切磋琢磨しましょう
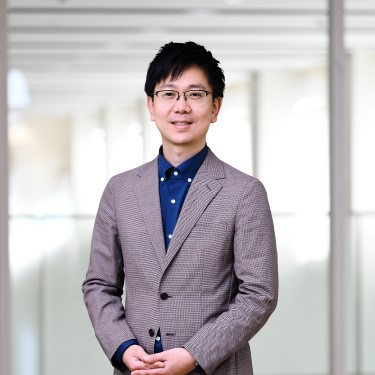
今西祐介 教授(総合政策学科)
私の専門は言語学(理論言語学、フィールド言語学)です。GCaPとはあまり関係がない分野に見えるかもしれませんが、実は言語は(国際)秩序や政策と密接に関連しています。私がこれまでにフィールド調査の対象として研究を行ってきたグアテマラ共和国のカクチケル語(マヤ語族)や奄美・喜界島の奄美語喜界島方言(琉球諸語)はUNESCOによって消滅危機言語に認定されています。UNESCOや言語学者の推計では、現存する約7000の言語の半分が21世紀の終わりまでに地球上から消えてしまうと言われています。私自身はこれらの言語の分析自体を専門としていますが、消滅危機言語が生じる社会的・政治的背景にも関心を持っています。
言語(あるいは母語)は話者やコミュニティーのアイデンティティと強く結びついているために、人類の歴史の中で、言語の抑圧が暴動や戦争に発展してしまった事例が多くあります。また、言語の消滅危機はグローバリゼーションの歪みとも言えます。なぜ言語が抑圧されるのか?消えていく言語を守る必要があるのか?あるとすると、なぜ守るべきなのか?そう簡単に答えが出せる問題ではありません。地球規模で起きている言語にまつわる問題について、GCaP生の皆さんと共に考えるのを楽しみにしています。
【略歴】
2007年に関西学院大学総合政策学部を卒業後、大阪大学文学研究科修士課程を経て、フルブライト奨学生(日米政府奨学生)として2009年マサチューセッツ工科大学(MIT)言語・哲学科博士課程に入学、2014年にPh.D. (Linguistics)を取得。2014年に本学総合政策学部助教に就任し、専任講師、准教授を経て2022年より現職。

三輪敦子 教授(国際政策学科)
アジアと日本の関係や、アジアの近代化の問題に関心をもったことから開発研究に引き寄せられ、また自身の社会人経験からジェンダーの課題に気づくことになりました。
当時、ジェンダーを冠した世界初の大学院とされていた英国サセックス大学開発研究所の「ジェンダーと開発」修士課程で学んだ後、日本赤十字社国際部や国連女性開発基金(現UN Women)バンコク事務所で勤務する機会を得ました。特に1995年の第4回世界女性会議(北京会議)の準備過程に携わったことにより、ジェンダー課題をどのように各国の政策課題とし、立法、制度、施策を通じて課題を解決していくかに関し経験を積むことができました。国連において「人権の主流化」が進み始めた時期でもあり、それらに導かれ、「ジェンダーと開発」「開発への人権アプローチ(human rights-based approach to development)の発展と実践」等の分野で研究を進めてきました。
政策との関連では、「女性と平和・安全保障(Women, Peace and Security: WPS)」に関する国別行動計画(National Action Plan: NAP)策定や、G7あるいはG20の議論に対しステークホルダーとして公式にアドボカシーを展開するエンゲージメント・グループであるC20(Civil 20)やW7(Women 7)に関わる機会を得てきました。
植民地主義を完全に克服できないまま、かろうじて保たれてきた、国連を中心とする多国間主義の将来を見通せないという深刻な危機を私たちは前にしています。GCaPの皆さんと「続く未来」をつくるための課題や変革の必要性について議論するのを楽しみにしています。GCaPで学び、「変革の主体(change agent)」として世界に羽ばたいてください。
GCaP履修者の声
瀬戸口 龍(2022年3月国際政策学科卒業)大阪府 敬愛高等学校出身
私は高校生の頃から漠然と海外に憧れがあり、競争の激しい環境でも生き抜いていけるように自分を鍛えたいと思いGCaPに登録しました。
実際にGCaPで出会った周りの学生はみなとてもアクティブに活動を行っており、授業の中で様々な視点からの意見が出たりプレゼンなどを通じて自分の意見を発信する機会が多くあり、周りの学生と切磋琢磨できたことはとても良かったです。さらに経験豊富な先生方からのお話を聞く機会が多くあり、自分の将来について考えを深めることもできました。
私自身の学習の大きなテーマである労働に関係する問題について学びたいという意欲から、2年生の時には交換留学でノルウェーへ行き、労働と社会福祉について勉強しました。ここから発展してゼミではワークライフバランスに関連する政策について研究しました。
私は将来、世界で抱えている労働問題の解消を仕事としたいと思い、労働問題に様々な方法で携わることのできる国際機関で働きたいと考えています。そのためにも日々の生活でなるべく英語に触れて仕事でも通用するレベルにして、自分の専門性をさらに深めて行きたいと思います。


松浦 未来(2022年3月総合政策学科卒業)兵庫県 芦屋国際 中等教育学校出身
1年次、カンボジアでのボランティア活動を通して気づいた途上国の現状。これが、私がGCAPへの登録を決意したきっかけです。
将来、世界を舞台に活躍できる人間になりたい、と考えていた私にとって、海外ビジネスの場で実務経験を積まれた先生方から、より実践的で手厚いご指導を受けることができる環境は大変魅力的でした。様々な分野でご活躍されてきた先生方から学ぶ内容は、本当に幅広く、自分の無知に気づかされる日々を過ごしました。
GCAPでは英語に触れる機会は勿論、社会情勢や国際問題への関心姿勢が常に必要とされ、世の中ゴトを自分ゴトに捉える習慣が出来上がりました。また、政策立案の考え方や、課題設定の置き方を学ぶことで、論理的思考力や問題解決能力を養うことができました。
2年次には、英語に囲まれた環境で学びをより深めたいと思い、カナダ留学に行きました。GCAPには志の高いメンバーと、私の意志を尊重してくれる先生方がいたおかげで、安心して「叶えたい」を追求することができました。
そして私は、この4月より、外資系企業で働くことが決まりました。「世界を舞台に」という野望を捨てることなく、GCAPで学んだ全ての知識や海外経験を活かし、実務経験を積みたいと考えています。



宇都宮 瑞希(2019年3月国際政策学科卒業)山口県 梅光学院高等学校出身
学部時代は、好奇心を絶えず追求した4年間でした。このような環境で、第一線でご活躍されている先生方にご指導いただけることはGCaPの大きな魅力です。
卒業後は英国の大学院で学びを続けました。大きな挑戦で不安に押しつぶされそうな時、先生方が力強く背中を押してくださったことを覚えています。また、卒業後もご相談に乗ってくださり大変心強かったです。勇気を振り絞って一歩を踏み出した大学院での生活は、人生においてかけがえのない経験となりました。私にとってGCaPでの出会いと経験は、チャレンジングな環境の中でも自分の可能性を信じ、乗り越えていくうえで、大きな糧となっています。
今後は、国家公務員として日本の平和と安全に寄与したいと考えています。これからも自分を信じて絶えず挑戦し、学びを続けていきたいです。




