2025.03.04.
Patricia Cabredo Hofherr氏 講演会を開催しました

講演の様子①
2025年2月16日(日)に、フランス国立科学研究センター主任研究員の Patricia Cabredo Hofherr先生をお招きし、講演会および研究交流会を開催しました。
午前の講演会では、「フランスのろう教育 ~過去・現在・未来~」と題し、講演の前半では16世紀にはすでに手話の存在が認識されていたこと、その後世界初のろう学校が設立されたこと、そして「第2回国際ろう教育会議(通称「ミラノ会議」)」により、ろう学校での手話の使用が禁止されたこと、などの過去のろう教育についてお話しいただきました。世界初のろう学校設立やミラノ会議について基本的な情報は国内にも入ってきていますが、ろう学校設立やろう児の教育にご尽力された方々やその経緯についてより深く知ることができ、貴重な情報をいただきました。

講演の様子➁
そして、講演の後半では主に現在のろう教育やろう者の高等教育機関へのアクセスについてお話しいただきました。フランスでは現在、フランス手話と書記フランス語のバイリンガル教育が一般的に行われているとのことでしたが、特にろう児自らが教育を受けたい言語を選択できる、そこにフランス手話も含まれているというところが日本のろう教育と大きく異なる部分で衝撃的でした。また、パリ第8大学では、ろう者が言語学について学ぶことができ、博士課程を修了できるまでの情報保障(手話通訳)も完備されているのも、日本とは大きく異なる点でした。講演の最後にはろうの研究者および博士課程の学生からのビデオメッセージがあり、ろう者の活躍ぶりを見ることができました。
参加者からは「フランスのろう教育や教育システムについて知れて大変勉強になった」「日本もバイリンガル教育の発展が課題だと感じた」などのコメントが多く寄せられました。
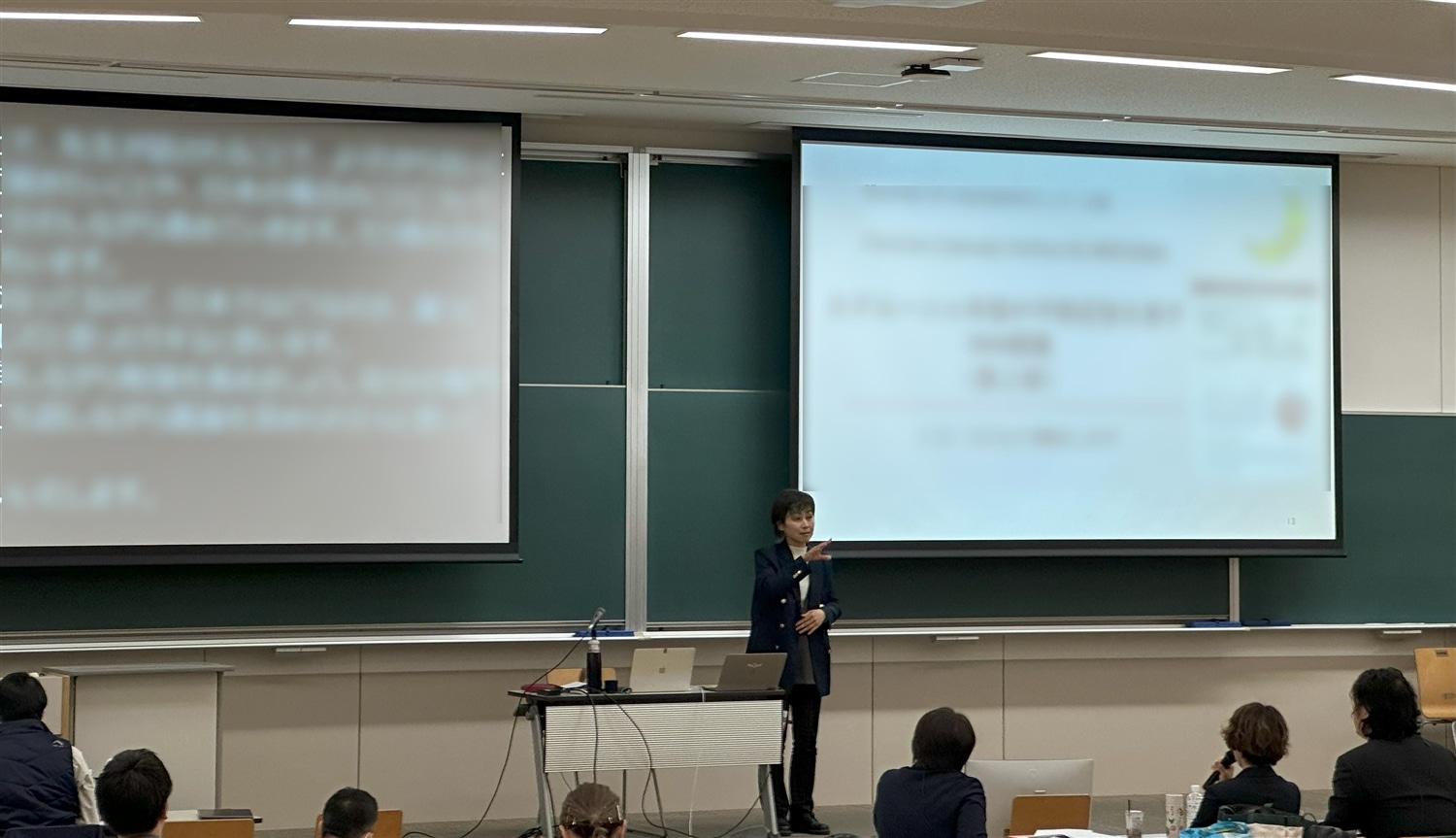
研究交流会の様子
午後の研究交流会では、「カタルーニャ手話の不特定性を表すNM標識」と題して、Hofherr先生の研究についてご発表いただきました。カタルーニャ手話では、人物が特定できない「誰か」という概念を表現する際、手指表現の他に空間とNMが共起されます。まず、空間について、「誰かがあなたのところに来た。私はその人を知らない」のような特定不明的(Specific Unknown)、または、「もし誰かが来たら知らせてね」のような非特定的(Non-specific)の文脈においては、話者の利き手側の上で表現されるのが一般的であり、これは日本手話にも似通った現象が見られるようでした。また、NMについて今回の発表では口角を下げる口型に特化され、特定不明的(Specific Unknown)の文脈において現れる傾向にあるということでした。口角を下げるNMは日本手話にも見られるようですが、参加者を交えたディスカッションから、どうやら異なる文脈で用いられるのではないか、というコメントがありました。これについては今後調査が必要です。
参加者からは「特定・不特定・既知・未知によって手型の位置や口角が変わることが興味深かった」「日本手話との違い、日本手話の特性も改めて確認できたのでよかった」など、充実した様子のうかがえるコメントをいただきました。
Hofherr先生をはじめ、Hofherr先生をご紹介くださった愛媛大学の金子真先生に厚く御礼を申し上げます。
また、ご参加くださった皆様、情報保障を担ってくださった日英通訳・手話通訳・文字通訳の皆様、本当にありがとうございました。

