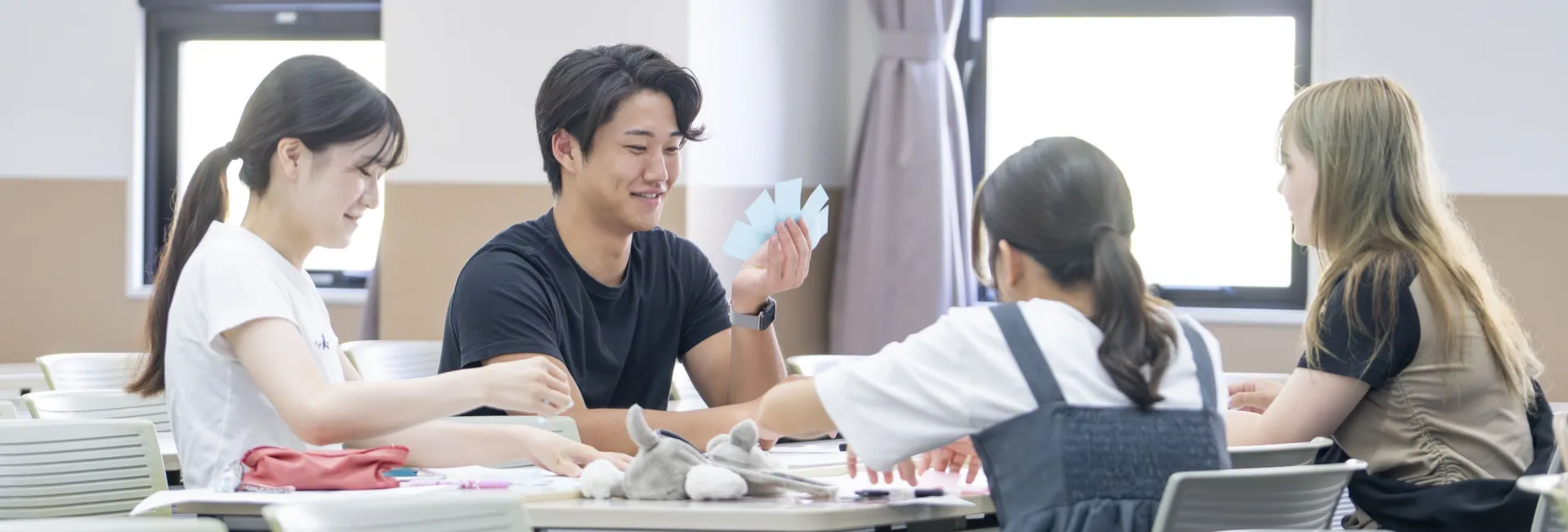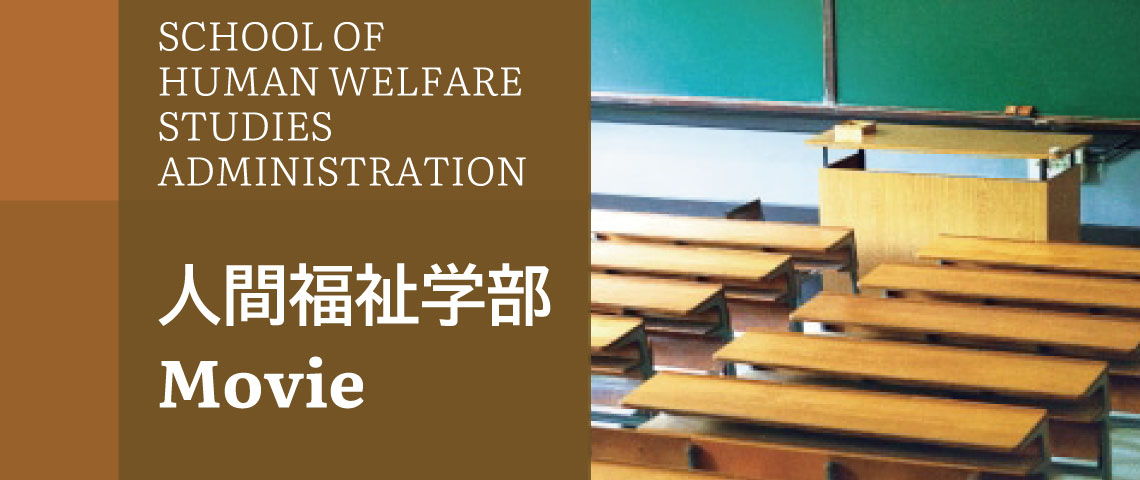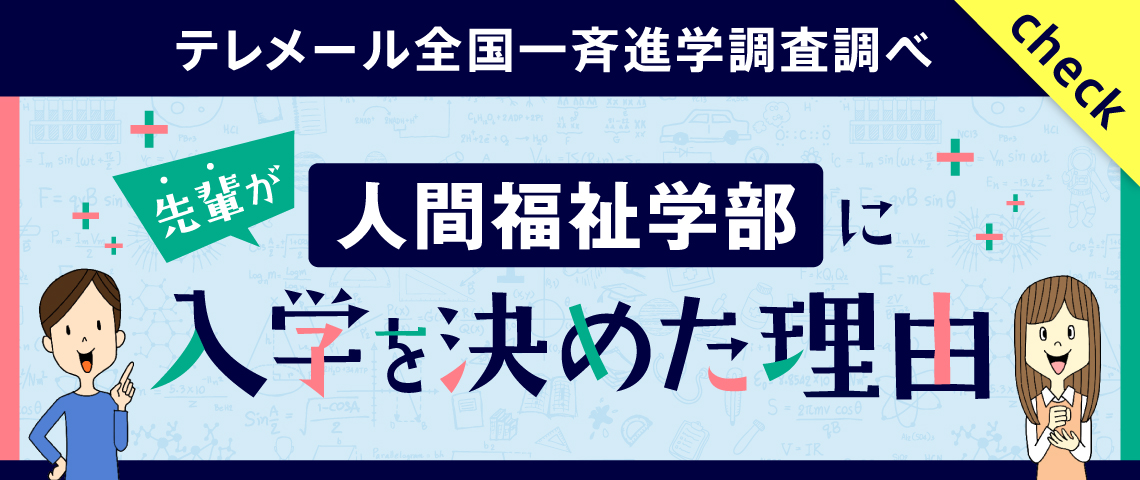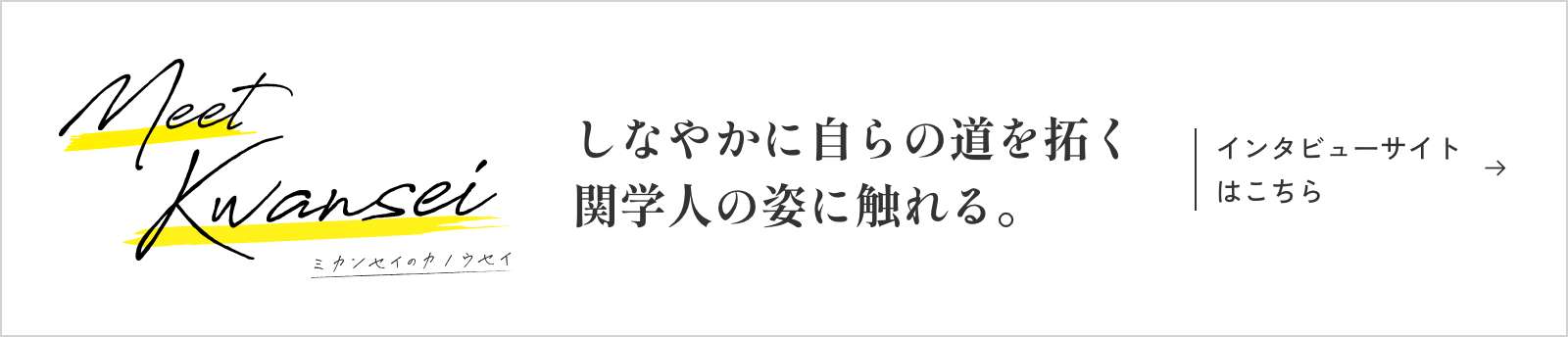人間福祉学部 School of Human Welfare Studies

「3つのC」を身につけ、
人間と社会、双方に関わる諸問題に
的確なソリューションを届ける
人間福祉学部では、「人間」とその生活環境である「社会」、双方に関わるさまざまな課題に対して、的確なソリューションを提供し、質の高い生活とよりよい社会の実現に貢献することを目指しています。そのために欠かせないのが「3つのC」です。「3つのC」を身につけるために、実社会での学びを重視した「実践教育」や学科融合型の科目を実施。多彩なカリキュラムを通じて、複雑に絡み合う社会課題に対し、新たな発想で立ち向かい、実践的な解決策を提案できる人材を育成していきます。
人間福祉学部の学びのポイント More About us
3学科に共通する専門科目の開講
どの学科でどんな専門的知識や技能を学ぶにあたっても、学生が共通して「3つのC」を身につけることを目指しています。特に「3つのC」の獲得の土台となる科目を「3学科共通専門教育科目」として開講。目的意識をもった学際的な学びを推進します。
3学科共通専門教育科目学科融合型の学びを推進
学生が学科の枠を越えて興味のある科目を履修することができるよう、3学科の学びが連携しています。場合によっては、学科を越えたゼミ履修も可能です。一つの分野を深化していくと同時に、他分野の視点・知識も積極的に吸収できる環境を整えています。
学科融合型教育多彩な現場での実践教育
自らの専門分野を深化させる学科ごとの実践教育と並行して、他学科、他分野のフィールドでも経験を積むことができる実践教育科目を設置。現場での実習だけではなく、事前計画の立案、事後学修による省察を綿密に行うことによって、一連の学びのプロセスを自身の糧として蓄積できます。
実践教育Global
海外の現場で実際に社会課題に触れ、解決策を考える機会を得るためのフィールドワークや海外留学プログラムを用意。異なる文化の中で生まれる課題を自らの目で確かめ、多様な価値観に触れることで、国際的な視野を広げることを目的としています。
Special
Interview
人間福祉学部インタビュー
分野の枠にとらわれない、
自由な学びが特徴の人間福祉学部。
どんな思いで学部を選んだのか。
今、何に夢中になっているのか。
その想いを学生や卒業生、研究者に聞きました。
進路について Career
未来を広げる多彩なキャリアの選択肢
人間福祉学部では、社会福祉、医療、教育、行政、企業など幅広い分野で活躍できる人材を輩出しています。さらに、大学院では専門性をより深め、研究や高度な実践力を身につけることができます。
学部長メッセージ Message
“Mastery for Service”を体現する学部を目指して
人間福祉学部長山 泰幸

教育の指針
新着情報 News
-
2025.12.04
-
2025.12.01
-
2025.12.01
-
2025.12.01
該当する情報はありません。