Interviews 卒業生 究極の人生の節目である「死」に、想像力をもって向き合う仕事

Introduction紹介文
犬塚さんがキャリアを見直すきっかけになったのは、大切な家族の死という強烈な体験でした。関学の科目等履修制度を活用して「死生学」と出合い、人が死ぬこと・生きることについて学びを深めることができたと言います。授業で得たものは、想像力をめぐらせて人に関わることの大切さ。価値観の違いを受け止め、寄り添う姿勢は、人生のリアルを現場で体感できる今の仕事にまるごと活かされていると感じる毎日です。
祖母との死別体験が「心が動かされる」キャリアを求めるきっかけに。
現在の仕事に携わる大きなきっかけとなったのは、祖母との死別体験です。関学を卒業し、社会人として働いていた頃、祖母が余命を宣告されました。大手企業に就職し、営業担当として3年目を迎えていた当時の私は、アイデンティティの構築を社名や肩書きといった社会的な評価を求めていたように思います。私が社会人としてできることが増えていくのとは逆に、祖母は今までできていたことができなくなっていく。その姿を少しずつ受け止めながら、自分にとって祖母は大切な人であり、価値は変わらない。私が今持っている肩書きを手放したとしても自身の価値が下がることはないのだと、生きることに向き合う祖母や家族の姿に、ストンと腑に落ちる気づきがありました。
それが転機となり「本当に自分がやりたいこと、どんな仕事ならワクワクできるだろう」とキャリアを見つめ直し、浮かんできたのが「人の人生の節目に関わること」でした。人生の節目と言えば冠婚葬祭。最終的には人の最期に関わる仕事を視野に入れ、まずはダブルワークで経験を積もうと、ウエディング業界へ飛び込みました。
「死生学」と出合い、人にはそれぞれの人生があり、自分の価値観で物事を決めつけないことを学ぶ。
ある時、ゼミの同期に、「人が生きること・死ぬこと」を巡る思考をさらに深め、言語化できるようになりたいと打ち明けたところ、関学の「科目等履修制度」で、藤井美和先生の「死生学」を学んでみては、と勧められました。この制度は、社会人や地域の人たちが大学や大学院で開講している授業科目を履修し、正規の単位を取得できます。私は半年間、人間福祉学部の「死生学」と人間福祉研究科の「死生学研究」を受講しました。
「死生学研究」の授業では、脳死など簡単に結論の出ないテーマについてディスカッションします。授業の最初の2回は、藤井先生を含む参加者が自身の半生を語る時間に充てられました。それぞれの人生背景をしっかりとつかむ時間が設けられたことで、真逆の考え方であっても、この人はこういう人生を過ごしてきたからこその価値観なのだと、受け入れられるようになりました。意見の違いを超えて人を理解する大切さ、そして「無理に答えは出さなくてもいいのだ」ということを学べたと思います。「死生学」の授業で得たものをひと言で言えば「想像力」ですが、自分の価値観で物事を決めつけないことを常に意識しながら、仕事に取り組んでいます。
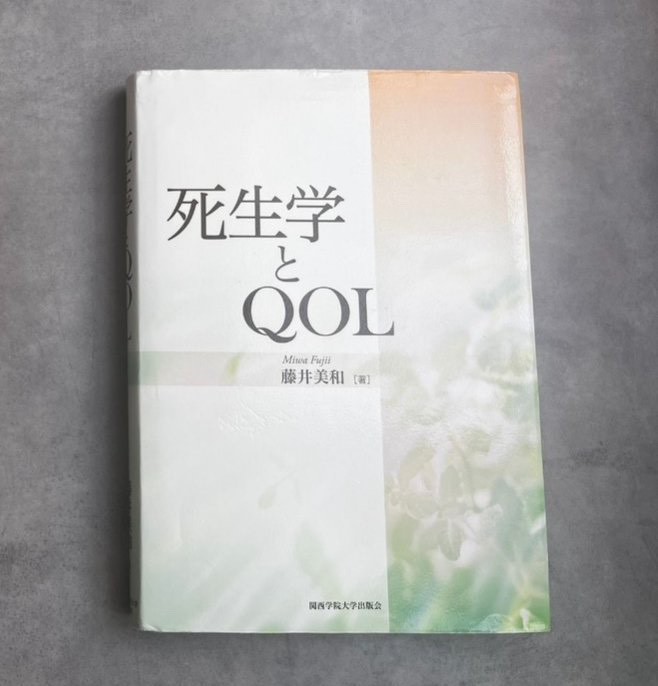
想像力をめぐらせて、人と関わることの大切さ。葬儀の仕事では「死生学」の学びがまるごと生きている。
現在は葬儀社で、喪主様との打ち合わせから葬儀内容のご提案、火葬に至るまで、残された方々が望むお別れの形を実現する仕事に携わっています。その前はウエディングの仕事と並行して、フリーランスの立場で葬儀にも関わっていました。人生の節目をプロデュースする方法を体系立てて自分の中にインストールするとともに、人の生や死をしっかりと学びたかったというのがその理由です。
藤井先生からは人の考えを理解するためには、自分の目の前の人の人生背景をどこまで想像力をめぐらせて関われるかという、人としての在り方の部分を教えていただいたと思っています。それは、今の仕事に置き換えれば、周りからは大往生と思える100歳を過ぎた死でも、ご家族にとっては深い悲しみであり、また自死であっても素晴らしい人生だったと拍手で見送りたい場合もあります。ご家族が望まれるお別れの形を、想像力を駆使して汲み取る際に、「死生学」の学びがまるまる生きていることを実感する場面が幾度もあります。「こういうお見送りができて良かった」とご家族の表情がやわらぐ瞬間や「その方らしい時間になった」と思える現場に立ち会えた時、この仕事のやりがいと深い意味を感じています。


「死」と正直に向き合うためには、自分が健康であること。「生」を扱う取り組みを、将来のライフワークに。
葬儀の仕事は、究極の接客業だと思っています。時にはご家族の感情に寄り添いきれず、戸惑う場面も少なくありません。自分自身の心身を整えることを大切にし、フラットな心持ちで仕事に向き合えるようにしています。毎日、死を見つめながら仕事に取り組んでいるので、いつかライフワークとして「生」にフォーカスし、さまざまな人の生きる姿を記録に残したい。それを仕事に活かせば、良い循環が生まれるのではないかと思っています。


