Interviews 研究者 人間の発想力を信じ、高性能二次電池の研究に活かす。

Introduction紹介文
ニュースなどでも目にするリチウムイオン電池。今、これに代わる新しい物質を活用した二次電池の開発が進められています。吉川先生は基礎から応用までを含めた研究開発を行う、日本における次世代二次電池研究のトップランナー。研究の現場でこれから主流となっていくであろうAIなどの最先端技術にトライしながら、人間が持つ「ひらめき」の必要性も感じているようです。「研究は楽しいものですよ」と語る吉川先生にお話を伺いました。
持続可能な社会を実現するために、資源や環境に配慮したポスト・リチウムイオン電池を創製する。
15年間ほどメインの研究として取り組んでいるのが、次世代を担う高性能な二次電池の開発です。二次電池は、充電池や蓄電池とも呼ばれ、くり返し使用できる電池のこと。では、皆さんが今使用しているスマートフォンやノートパソコンなどのモバイル機器に広く使われている二次電池が何でできているか知っていますか?
正解は「リチウムイオン電池」。リチウムはレアメタルのひとつとして知られ、急速に需要が伸びている資源でもあります。実はこのリチウム、埋蔵の分布が偏っていて、日本ではほとんど産出されません。さらに政情不安や紛争といった世界情勢の変化による供給リスクやコストの高騰も懸念されています。
そこで日本でも産出が可能な資源を用いた、リーズナブルで環境にも配慮したポスト・リチウムイオン電池の開発が求められています。実現すれば、再生可能エネルギーを始め、さまざまな分野での利用が期待できる可能性を秘めています。

次世代の二次電池に最適な材料を探索。最先端の情報科学と人間の持つ「ひらめき」の相乗効果で候補物質を発見。
リチウムに代わる、次世代の二次電池として特に注目を集めているのが、レアメタルを使わないナトリウムイオン電池です。しかしどのような電極材料が最も適しているかは、まだわかっていません。現在、数十万種にも及ぶビッグデータから、AIや機械学習アルゴリズムなどの技術(マテリアルズ・インフォマティクス)を用いて、材料となる物質を探索しています。そしてもうひとつ、これまでの研究実験や論文をベースに得た経験や知識の蓄積から生まれる「勘」、いわゆる「人間の直感やひらめき」で物質を探り当てる、ある意味アナログ的な手法も取り入れています。
膨大なデータを解析するには、AIなどコンピュータの方がスピーディかつ効率的です。しかしAIにはなくて、人間にはある「情緒」が、時に研究開発においてAIを超える働きを見せることがあります。人間が持つ発想のひらめきや勘は、まだまだ捨てたものではありません。現在のAIでは届かない領域を人間がカバーする。情報科学の技術と人間の直感を併用したことで、より精度の高い候補物質の発見につながったと思っています。
見聞を広め、世の中のさまざまな物事をインプットする。センスを磨き、内面を豊かにすることも科学者には必要。
私は高校生の時に、物質が示す性質や色に興味を持ったことで化学が好きになり、大学で化学を専攻、博士課程を経て研究者になりました。ナトリウムイオン電池の材料として、世界中の科学者が注目している物質のひとつに「プルシアンブルー」があります。これは、江戸時代の絵師・葛飾北斎も使った青色絵の具の一種。歴史ある絵の具(染料)の多くに、化学材料が用いられています。この染料が次世代電池の材料になるのではというひらめきは、芸術や文化・歴史を理解していないと出てこない発想です。私は常々「科学者は芸術家である」と思っています。理系の知識や技術の習得はもちろん、ジャンルにとらわれず見聞を広め、ひらめきの種をインプットしておくことも大切です。私が師事する先生も「美術館へ行け」とよくおっしゃられていました。私は今でも海外・国内の出張で美術館を巡る時間を作り、センスを磨いています。
化学の研究は「0→1」を目指しますが、立てた仮説通りになった場合、「1」は超えられないという気がしています。自身が持つ発想力を駆使して「1」の先にたどり着くのも、物理や数学とは異なる化学研究の醍醐味ではないかと思い、研究に取り組んでいます。

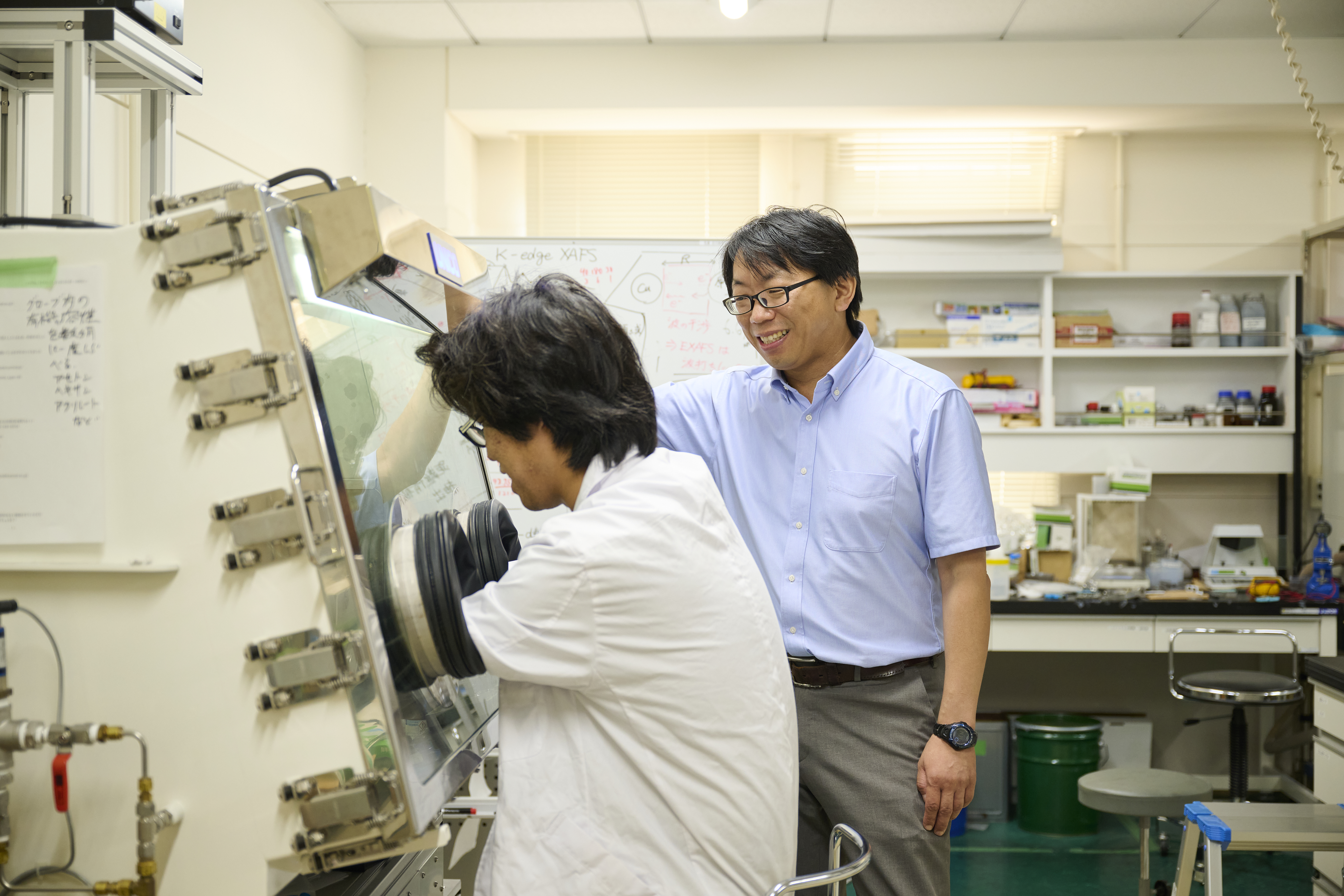
若い世代の研究ファンを増やすのが目標。
将来は学生とともにベンチャー企業を立ち上げたい。
「なぜ?」を解き明かす知的好奇心は、人間が持つ最大の魅力です。研究は楽しいものなので、若い世代を「研究ファン」にして、研究者になりたいという子たちを一人でも増やしていきたいですね。「感動」は、人生を実り多いものにしてくれます。現在、研究者志望の学生が3名も在籍してくれています。ほぼ研究仲間でもある彼らの力もあわせて、世界を変えるような材料や二次電池を実現し、ベンチャー企業を立ち上げたいと考えています。


