Interviews 学生 日本を内側と外側から見て、長年の「なぜ?」に答えを

Introduction紹介文
高校生の頃から「日本はなぜ、成長していないと言われ続けているのだろう?」と不思議に思っていたという林さん。その疑問を解明するために選んだのは経済学部でした。大学では学部の勉強だけでなく海外経験やボランティア活動へも積極的に取り組み、多彩な経験から視野を広げ、今は最終学年生として全力でゼミ活動に取り組み中。ゼミ仲間とのディベート活動や卒業論文に向けた研究では、これまでの貴重な経験が生きていると語ります。
日本経済への興味と、海外への好奇心。
知りたいこともやってみたいことも、関学だから挑戦できた。
1990年代から日本経済は「失われた20年」と表現され停滞していました。それがいつの間にか「失われた30年」まで延び、高校生の私は「なぜ日本はずっと成長していないんだろう?」と疑問に思うように。その疑問を掘り下げて学びたいと志望したのが経済学部です。他大学ではなく本学を選んだのは、留学に関するサポートが手厚いから。海外にも関心があり、留学を視野に入れながら英語力を磨いていたので、充実した支援制度に魅力を感じました。学部の4年分の学びに交換留学した1年を加え、現在は5年目の最終学年。チャレンジ精神と知的好奇心を原動力に、たくさんのことを経験してきました。

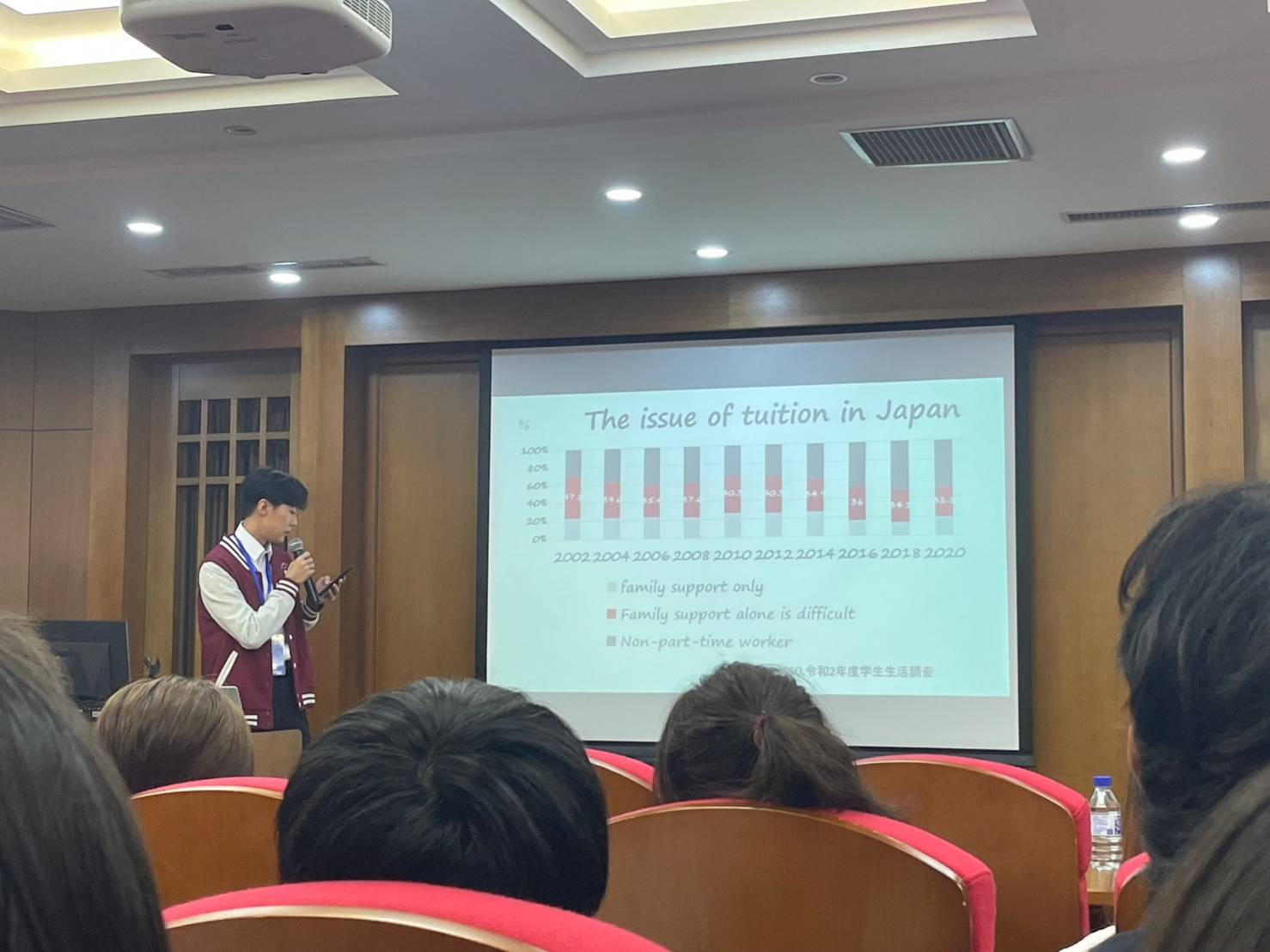
「自分から動かなくちゃ、何も変わらない」
視野を大きく広げてくれた海外でのさまざまな体験。
2年生の時にはウクライナ支援のボランティアに参加し、オーストラリアとポーランドに滞在。3年生では中国・吉林大学への短期留学、4年生ではドイツのアウグスブルク大学で1年間の交換留学を経験しました。中でもドイツでの生活は多様な価値観と向き合う日々で、われながら大きく成長できたと思います。初めこそ言葉や文化、それぞれがもつ背景の違いに戸惑いもありましたが、自ら積極的に動き、相手を理解しようとすることで人間関係が深まることを実感。物事を一方向からだけでなく、多様な背景から捉えることの大切さを学びました。また他国の留学生やドイツ人学生たちとの交流を通じ、日本を外側から見る視点を養えたのも留学したからこそだと思います。留学中のいちばんの思い出は、ドイツ人の友達の実家に1週間ほど滞在したこと。ドイツの暮らしや家族の会話、伝統を肌で体験でき、特に食事中に議論が始まるなど日本では見られない文化に触れました。
ゼミ活動では仲間とのディベート活動に熱中。
卒業研究で、高校時代からの疑問に答えを見つけたい。
帰国した今、最も力を入れているのがゼミ活動です。所属するゼミは「日本の産業競争力」を大きなテーマに、共同研究とディベートに力を入れているところ。大人数のゼミですが、みんな意欲的で刺激を受けながら活動できる環境です。ディベート活動は年に3回、大きな発表の場があり、たとえば「小泉構造改革は正しかったのか」や「ふるさと納税は是か非か」といったテーマを肯定・否定の2チームに分かれて議論します。説得力のある主張をするには資料の準備と論理の組み立てがとても重要。準備にはたくさんの時間と労力をかけ、チームで何度も話し合いを重ねます。意見がぶつかることもありますが、それを乗り越えて一つの議論をつくり上げたときの達成感は格別です。また現在は卒業論文にも取り組んでいます。テーマは「日本が成長するために必要なこと」。日本の産業構造を他国と比較し、経済成長のヒントを見つけることを目標にしていて、特にIT投資が中小企業に与える影響をドイツの事例と比較しながら研究中です。知らなかったことを知る瞬間はいつも楽しく、データ分析で仮説通りの結果が出るとワクワクします。高校生の頃から感じていた日本の成長鈍化への疑問を、自分なりに解き明かすのが楽しみです。


2年生の頃から続けてきたボランディア活動。
能登半島を再び訪れ、今できることで改めて貢献したい。
コロナ禍、外出もままならない中で大学へ入学した私にとって、困難な現場を訪れて復興に貢献するボランティア活動は“挑戦”を象徴する原体験です。大学2、3年生の時には国内外のさまざまなボランティアに参加。2024年の能登半島地震発生直後にも現地を訪れ、被災者の方向けの足湯スタッフ、食料の配給係、心のケアを意識した話し相手などを担当しました。学生でいられる期間も残り少なくなった今、再び能登半島のボランティアに志願しようと考えています。


