Interviews 学生 将来は公認心理師として社会に貢献したい

Introduction紹介文
「何の分野を学べば将来の役に立ち、かつ社会に貢献できるのか」を考え、心理的支援を必要とする人たちを手助けする公認心理師を志して本学科に入学した井戸さん。授業を通してさまざまな心理学にふれ、多くの発見や気づきを得た経験が、日常生活を多角的な視点で見ることにもつながっています。レポートや課題に苦労しつつも、仲間と力を合わせて乗り越えながら、サークル活動など日々の学生生活も楽しんでいます。
心理的支援を必要とする人の助けになりたいと、公認心理師を目指して本学科へ。
多岐にわたる心理学を興味深く学んでいる。
公認心理師の資格を取得したいと考え、本学科に進学しました。高校生で進路を選択する際、何の分野を学べば将来の役に立ち、かつ社会に貢献できるのかを考えました。そこで着目したのが、日本の自殺率の増加と心理的支援の重要性です。心理的支援を必要とする人たちの現実をメディアやSNSを通して知る中で、要支援者が困難な状況から立ち上がるための手助けがしたいと思うようになりました。
また、高校までの10数年を生きてきた中で、自分自身が傷ついた経験や、周りの人が傷ついているのを目の当たりにした経験もあり、心の問題を身近なものとして感じていたのもこの道に進んだ理由の一つです。
大学で実際に学び始めてみると、心理学の分野の広さと懐の深さに驚きました。脳の構造、統計学、適切な教育のあり方など、それぞれ全く違う分野のように感じるものも、すべてが心理学に内包され、深く結びついていることを、高校生の頃の私は知りませんでした。これまでは漠然とした疑問だった「心の捉え方」を具体的に学ぶことができるので、自ら興味を持って勉強に取り組めています。
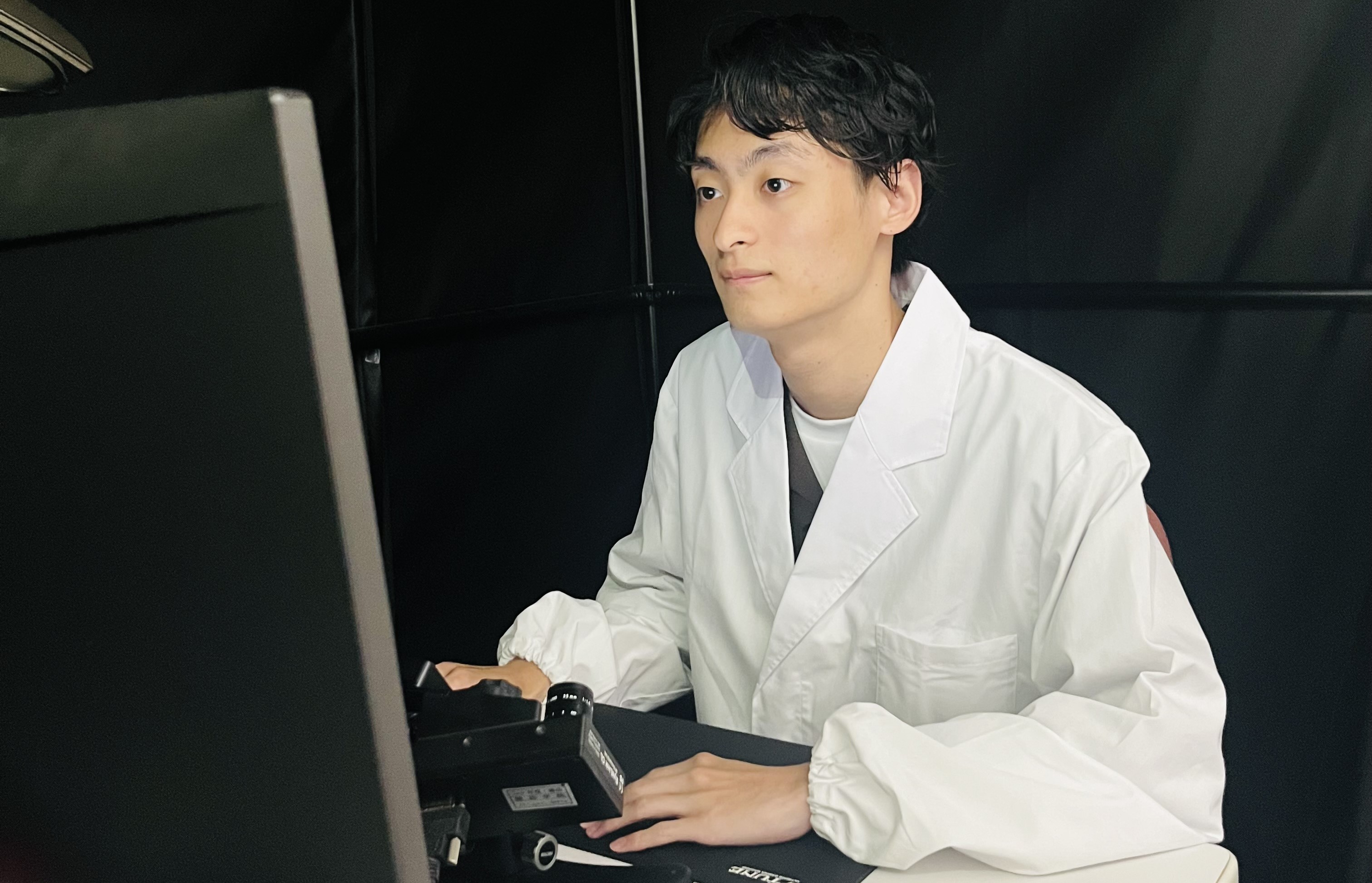
心理学を学ぶことは、新たな発見や気づきの連続。
日常生活を多角的な視点で見る技術を身に付けるのはとても面白い。
多種多様な分野の心理学にふれると、たくさんの発見や気づきが得られます。例えば、知覚心理学の授業では、視覚情報が実際とは異なるように知覚される「錯視」という現象について学びました。「なぜ目の錯覚が起こるのか」「実験方法や条件を変えるとどうなるのか」など錯視のメカニズムをひも解いていく過程は、とても新鮮で驚きのある体験でした。他にも、教育心理学や学習心理学の授業では、「自分の方法は、こういうところが理にかなっていたのか」と今までの勉強法についての疑問が解決したり、「こんなやり方があったのか」と今後の勉強法を改善するヒントを得たりしています。心理学を通して日常生活を多角的な視点で見ることができるのはとても面白いです。
授業で新しい知識を得るのは楽しいですが、その一方で、日々のレポートや課題は大変です。特に苦労しているのは、4週間に1回課される実習授業のレポート。4~5名の班に分かれて取り組むのですが、実験内容から自分たちで考え、計画を立て、実際に実験をして、得られた結果とそれに対する考察をまとめなくてはいけません。班の仲間と共に頭を抱えながらも、みんなで協力して毎回なんとかレポート提出に漕ぎつけています。
空き時間や授業の後は、図書館で課題やレポートを進めていることが多いですが、昼休みは中央芝生で友達と弁当を食べるのが良い息抜きになっています。室内で食べるよりも晴れやかな気分になるので、お気に入りのひとときです。
目下の目標は国家資格の取得。
息苦しい現実を生きる人たちをサポートできるように、もっと勉強して知見を深めていきたい。
今の目標は、心理職の国家資格である公認心理師を取得することです。公認心理師が働く現場としては、病院や福祉施設、学校、企業といったさまざまな選択肢があり、まだ具体的な進路は決めていませんが、資格を生かして自分なりに社会に貢献できる道を模索したいと考えています。近年はSNSが発達し、一般の人たちが自分の困難な現実や精神的負荷について吐露できるようになり、その声を誰もが簡単に閲覧できます。私自身も、息苦しい現実を生きる人たちの声をよく目にしています。心理的支援を必要とする人たちを助けることができるよう、大学で心理学に関する知見をもっと深めていきたいと思います。

自然の中で交流するサークル活動を通じて、子どもたちと一緒に自分自身も成長したい。
公認心理師の仕事では、大人だけでなく子どもに対応する可能性もあります。そのため、将来に向けて子どもと接する経験も積んでおきたいと思い、自然の中での活動を通して子どもと交流するボランティアサークルに参加しています。子どもへの対応だけでなく、保護者や他のメンバーとの連携など、学ぶことが多くて大変ですが、ワクワクした表情で遊んでいる子どもたちから元気をもらいながら、自分たちも楽しんで活動しています。


