Interviews 研究者 ハイブリッド材料を創出し、社会に貢献する
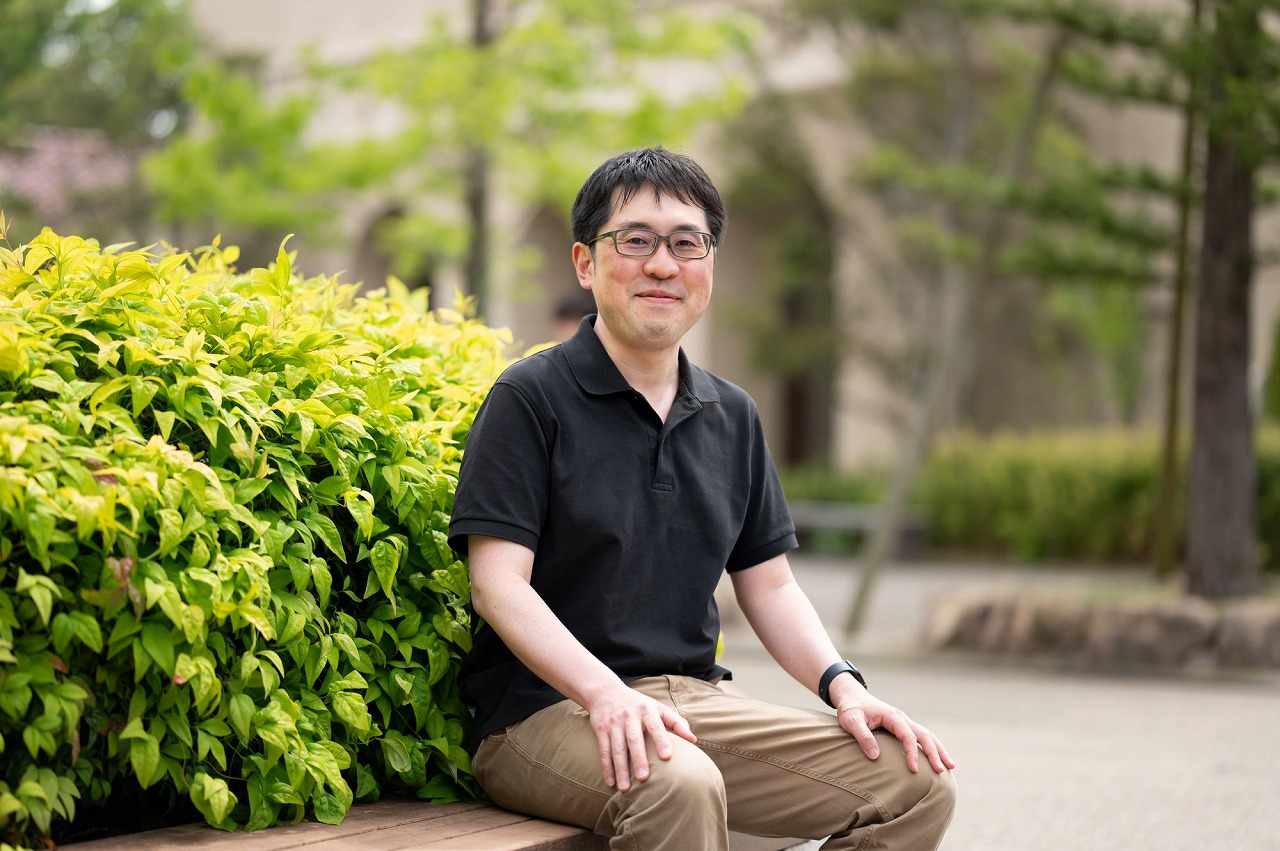
Introduction紹介文
有機無機ハイブリッド材料として注目される金属有機構造体(MOF)に、学生時代に出会い、この分野の黎明期から研究に取り組んできた田中先生。専門である錯体化学の知識を生かし、ナノテクノロジーや分子エレクトロニクスにも携わってきました。また、研究に人工知能を取り入れるなど、他分野との融合にも積極的にチャレンジしながら材料開発を進めておられる田中先生に、現在の研究内容や社会貢献への思いについて伺いました。
錯体化学の技術を駆使して、有機物と無機物の両方の性質を併せ持つハイブリッド材料の創出を目指す。
金属有機構造体(MOF)に電気を流す特性を与え、社会を支える機能性材料の開発に取り組んでいる。
私が専門とする錯体化学は、金属イオンと有機分子(配位子)が結合して形成される化合物(金属錯体)を研究する分野です。金属錯体は有機物と無機物の両方の性質を持っているため、例えば有機物であるプラスチックと無機物である金属の「いいとこ取り」ができる可能性を秘めた素材として、有機無機ハイブリッド材料とも呼ばれています。
錯体化学の分野の中で、特にこの20年ほど注目されているのが、金属有機構造体(MOF:Metal Organic Frameworks)です。MOFは、構造の中に小さな穴がある「多孔質」という特徴を持つため、その穴を利用して水素や二酸化炭素などのガスや分子を貯蔵できるのではないかと期待されています。また、MOFは基本的に電気を流さない材料ですが、私の研究室ではMOFに電気を流す特性を与えることで、二次電池電極材料や電子デバイスにも応用できるのではないかと考え、研究に取り組んでいます。

黎明期からMOF研究に携わってきただけでなく、他分野との融合領域も経験。すべてが現在の研究に生かされている。
私の学生時代の指導教員だった京都大学の北川進先生が、1997年にガスを取り込む材料として発表したのが、MOFの最初期の報告だと言われています。私が学部生として北川研究室に入ったのが2002年ですから、MOF研究のまさに黎明期。世界的に盛り上がっている研究の中心地に身を置けたのは、とても貴重な経験でした。
その後、ドイツのアーヘン工科大学に留学し、MOFとナノテクノロジーを融合した研究に従事。帰国後は大阪大学で、錯体化学の知識を使いながら分子エレクトロニクスの研究に携わりました。このようにMOFだけでなく他の分野にも関わったことで得られた知見が、MOFに電気を流す特性を与えるという現在の研究につながっています。実は、学生時代に北川研究室に入ったときの最初のテーマは、MOFではなく有機EL材料だったのですが、当時の経験も現在の研究に生かされています。

オリジナリティのある研究を生み出そうと試行錯誤を重ねる中で、材料化学と情報工学の融合領域を開くことができた。
2015年に本学に着任し、今年10周年を迎えました。最初の数年間は、どのような研究を行えば自分の研究室のオリジナリティを出していけるだろうかと悩んで、さまざまな研究手法を試していました。大きな転機となったのは、2017年にJSTの「さきがけ」というプロジェクトに採択され、AI技術による材料探索にチャレンジする機会を得たことです。AIに関する知識や経験は全くありませんでしたが、学内の情報工学の専門家に相談し、共同研究として取り組んでいく中で、材料化学と情報工学を掛け合わせるという、当時はまだあまり一般的ではなかった融合領域を開くことができました。
革新的な材料を開発し、カーボンニュートラルの実現の基盤となる技術を提供して、エネルギー問題の解決に寄与したい。
MOFに電気を流す特性を与えるという、現在私たちが進めている研究は、エネルギー問題の解決に貢献できるのではないかと考えています。例えば、太陽光エネルギーを使って、水を水素と酸素に分解する光触媒反応という現象がありますが、この反応の触媒として、私たちが研究している材料が良い性能を示すことが明らかになってきました。この材料をうまく活用できれば、二酸化炭素を排出せずに水素を生成する技術につながるかもしれません。他にも、東京科学大学との共同研究で、太陽光エネルギーを使って二酸化炭素を炭素化合物へと変換する光還元反応によるクリーンなエネルギーの創出にも取り組んでいます。こういった研究を通して、カーボンニュートラルの実現の基盤となるような技術を提供できればと思っています。


基礎研究だけにとどまらず、社会実装を見据えてより良い材料を開発していきたい。
今私が取り組んでいるのは、いわゆる基礎研究です。基礎研究には「こんなことができるんだ」という驚きや発見があり、やりがいも意義も非常に大きいと感じていますが、やはり次に目指したいのは、社会で実際に使われるような材料を開発すること。現時点では、耐久性や安全性、さらにコストや効率の面でも、まだまだ至らない点があります。社会実装を見据え、より良い材料の開発を目指して引き続きチャレンジしていきます。


