Interviews 研究者 生きることの意味、教育の意味を問い続けていく

Introduction紹介文
大学在学中に芽生えた「人間とは何か」という関心を深めるために、改めて学士編入し、大学院に進学。フランクルの臨床哲学や京都学派の哲学、物語論を手法とする臨床教育学、東西の宗教思想などと取り組みながら研究を進めてきました。教育哲学や教育人間学の分野で、生きることの意味や教育の意味といった簡単に答えの出ない問いに向き合ってきた岡本先生に、研究内容や社会にもたらす価値について伺いました。
[プロフィール写真は、鳥のさえずり、風の音、子どもたちの声が共鳴し合う岡田山(NSC)にて撮影]
人は何のために生きるのか。教育は何のために営まれるのか。生きることの意味や教育のあり方について考え続けてきた。
意味喪失の時代を生き抜くために「人間と教育」を語り直す。自分自身の内面と時代背景から生まれた研究テーマ。
子どもの頃から、「人は何のために生まれてくるのだろう」と考えたり、ふとした瞬間に「大宇宙の中に自分がぽつりと独りでいるようだ」という気持ちになったりすることがありました。今は教育学部の教員をしていますが、私自身はどちらかというと学校に適応しづらいタイプだったと思います。学生時代、研究への内面的なモチベーションとなったのは、物質的に豊かな時代に生きているにもかかわらず、精神的に空虚に陥りがちな自己の存在意味を問い直すことでした。ちょうどその時期に教育思想の分野は、近代教育学批判のうねりの中にあって、従来の教育学の存在意義が根本から疑われる状況に直面していました。そういったことが重なり、ニヒリズム(意味喪失の時代)を生き抜くために、どのように「人間と教育」を語り直せるか、という問いと自分なりに格闘し始めることになったように思います。
フランクルの臨床哲学を手がかりに、受苦するという本質を持った人間という存在から、人間形成の風景を描き直す。
ヴィクトール・フランクルの臨床哲学や京都学派の哲学、物語論を手法とする臨床教育学、あるいは東西の宗教思想を手がかりに研究を進めてきました。特に、私が取り組むテーマに大きく関わるのは、フランクルが提唱した「ホモ・パティエンス」という人間理解です。精神科医で哲学者でもあったフランクルは、ナチス・ドイツの強制収容所に収監された経験をもとに『夜と霧』を書いたことでも知られる人物です。フランクルは「ホモ・サピエンス(知性の人)」に対置する言葉として、「ホモ・パティエンス(受苦する人)」を提唱しました。自律性・能動性を標榜する「ホモ・サピエンス」に対し、「ホモ・パティエンス」は身体によって世界と交わり、世界から影響を「被る」受動的な存在です。私はこの「ホモ・パティエンス」から人間形成の風景を描き直すことを目指しています。
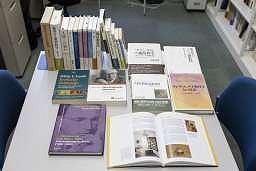
子どもに教える前に、まずは大人から。自分を開き、苦しみを受けとめながら、「聴く」という在り方への転換。
現代という意味喪失の時代において、教育のあり方を捉え直すためには、「生きる意味」の問題が究極的な関心とならざるを得ません。しかし、その人独自の「生きる意味」は、他者が教えることなどできない。ここに大きなパラドックスがあります。目的合理主義的な発想で、教育を矮小化しすぎたことが、近代の教育システムの限界や矛盾につながっているのではないかと私は考えています。教育者にとって最も大切なのは「聴く」ことです。海の波の形が1つとして同じでないように、人間関係の中で起きる状況はすべて1回限り。自分を開いて、苦しみも受け入れながら、その状況が何を呼びかけているのかを「聴く」ことができないと、生きた関係性は生まれません。子どもに何かを要求する前に、大人がまず「聴く」という在り方に転換することが大切ではないでしょうか。
意味を見失いがちな現代。だからこそ、簡単に答えの出ない問いにじっくりと向き合う学問の意義がある。
私が専門としている教育哲学や教育人間学は、教育学の中でも「基礎学」にあたる分野。「人間は何のために生きるのか」「教育は何のために営まれるのか」など、答えはすぐに出ないけれど重要な問いについて、じっくりと考えていく学問です。学生の皆さんにはこの学問を通じて、自分の人間観や教育観を常に問い直し、内的成長を遂げていく思考回路をつくってほしいと願っています。この思考を築くことなく、現実に適応することばかりを考えていると、社会に出て数年経った頃につまずいてしまうかもしれません。生きる意味を見失いがちな時代だからこそ、人文学を学ぶ意義があるのではないかと思います。
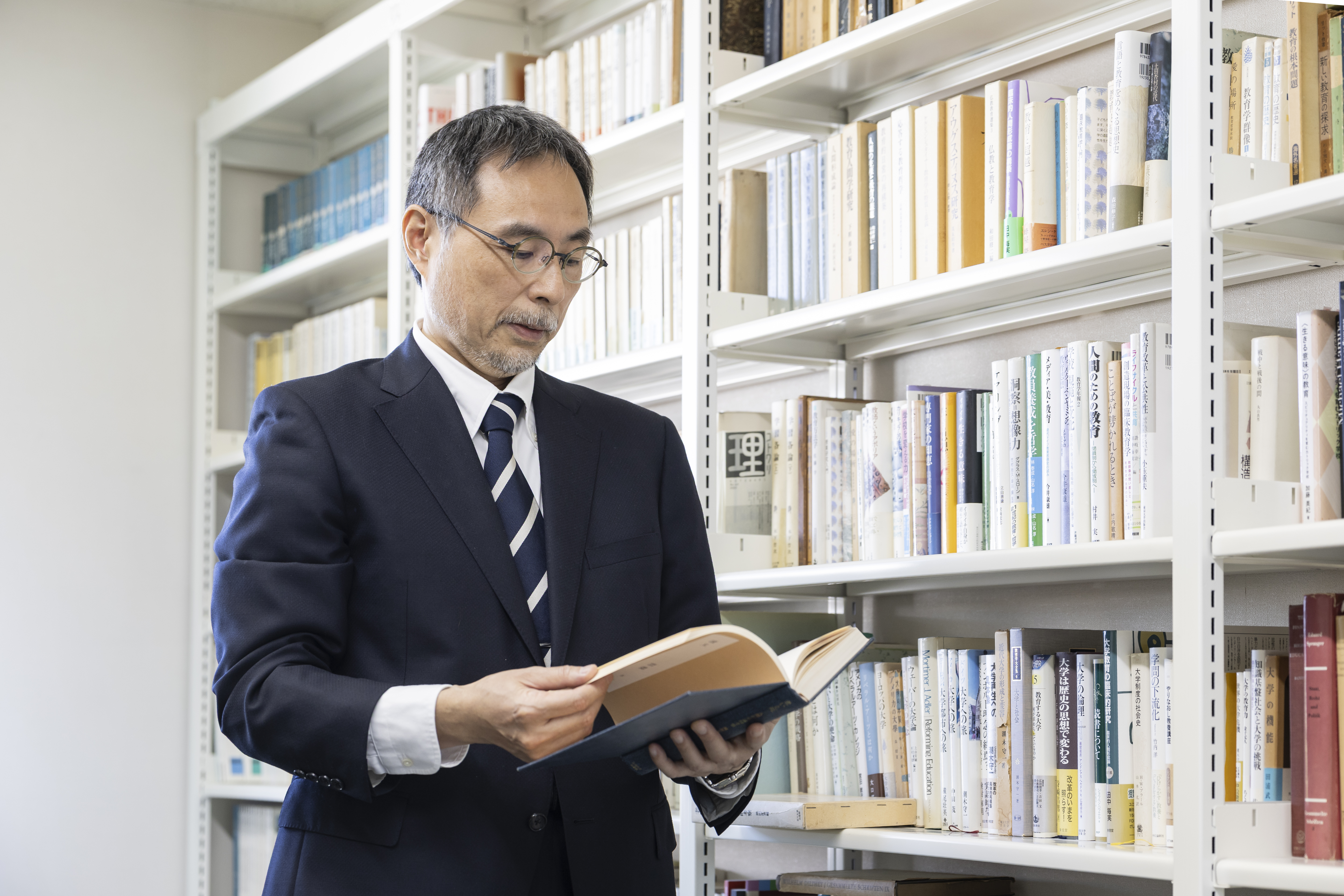
人間存在の有限性を深く自覚し、「存在の謎」を「謎」のまま育てていく
ソクラテスの「無知の知」という言葉は、今の時代にこそ大切な生きる構えだと考えています。これは、自分に知識が足りないことを自覚している、という意味ではありません。たとえテクノロジーがいかに進歩しようとも、人間が有限で不完全な存在であることをなおも自覚せよということなのです。私たちの日常の営みの底に「存在の深い謎」が隠れていると知ることが大切です。その上で人と人、人と世界が相互に形成し合う風景を描き出していくことが、私の研究の使命だと思っています。


