総合政策学部 総合政策学科
現代社会の課題を発見・
解決し、「共生の社会」
の構築をめざす
総合政策学科の学び Study
総合政策学科でできること
企業・NPOなどと連携しキャンパスの外に出て実践的に学ぶ
国内外問わず、キャンパス外でさまざまな調査を行うフィールドワークを実施。また、外部の研究機関や自治体、民間企業と連携し、さまざまな課題の解決に挑戦し、政策立案・提言を実地で学びます。
学際的なカリキュラムで総合的な視点を養う
法学、政治学、経済学、社会学、社会福祉学、工学、言語文化に関する科目のほか、複数の学問領域にわたる科目も設置。学際的な学びによって、総合的な視点と課題解決力を育みます。
共生をテーマに3つの領域から目標に合わせた履修ができる
共生をテーマに「自然環境」「社会・経済・技術システム」「言語・文化・思想」の3領域から、目標に合わせたさまざまな科目を履修可能。複合的な視点や方法論で、諸問題の解決策を考察する力を養うことができます。
4年間の流れ
公共選択論
本講義の目的は、学生が、経済と政治・行政の相互依存関係や政策決定メカニズムを公共選択論の理論や概念を通じて理解し、各政策領域における政府の失敗や政策の失敗の実態とそれを抑止する制度改革のあり方、社会・経済にとって望ましい政策のあり方を議論し、問題解決の方策を考える能力を養うことです。関西学院大学KSCと慶應義塾大学SFCのキャンパス連携授業として行います。

環境政策論
この授業の目的は、通常の講義を基本としながらも質疑のやりとり等のコミュニケーションを通じて、学生が環境政策の歴史や政策課題を理解し、環境政策に関する分析、考察、提案する能力を高めることです。

公共政策課題研究A【国際貿易の発展と税関】
国際貿易の中で重要な位置を占める税関手続きとその関連政策(WTO/EPAs関連を含む)について、毎回、神戸税関の現役職員など実務家が講師となり、実際的で具体的な知識を学生と共有することを目指す。将来、国家公務員を目指す学生はもちろん、国際物流・貿易関連の仕事につくことを考えている学生にとっても包括的かつ実際的な知識を得る機会となることを期待します。

卒業研究テーマ(抜粋)
- 環境配慮的行動の規定要因 〜レジ袋有料義務化の効果の検証〜
- フェアトレードの現状と課題 〜今後のコーヒー産業の在り方について〜
- フェノロジーカレンダーは地域活性化の有効な手立てとなり得るのか
- 日本の山間地域における過疎問題の改善に関する考察
- 中小企業の成長指標と存続・成長要因に関する考察
- 中国の中等教育機関における日本語教育の現状 ー口頭表現能力の重視に対する日本語学習者の要望と現実ー
- 地球温暖化を防止するには、どのようなエネルギーを活用すればよいのか
学部カリキュラム・履修モデル
進路について Career
将来の選択肢を広げる資格取得
総合政策学科生は「教育職員免許状中学校一種(英語)(社会)/高等学校一種(英語)(公民)」をはじめ、「学校図書館司書教諭」「博物館学芸員」などさまざまな資格を取得可能です。
社会につながる研究 For Society
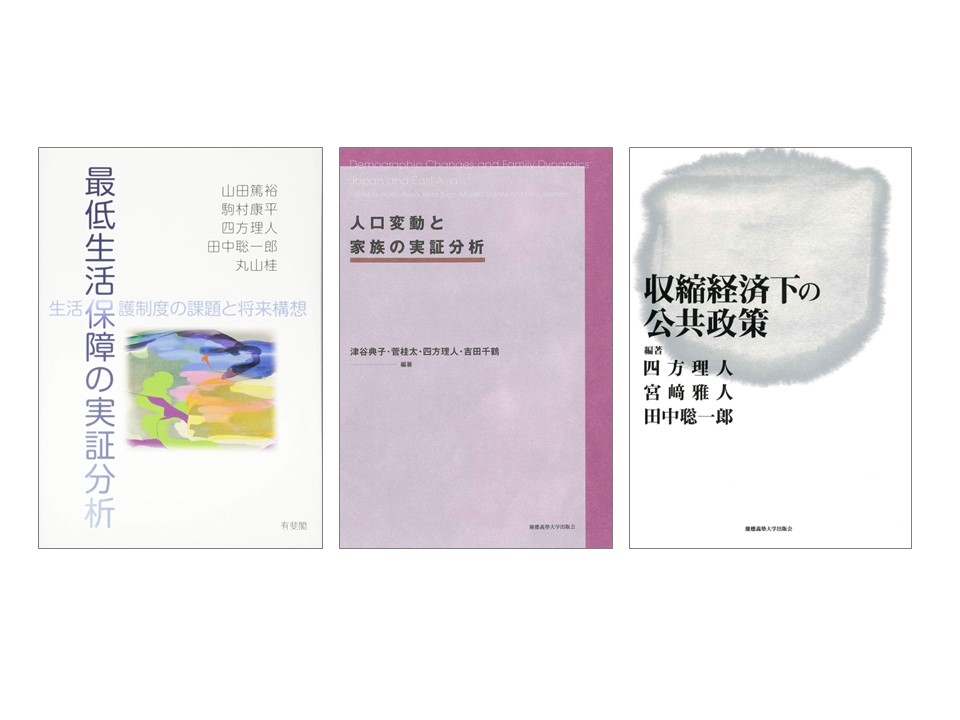
現代社会における所得格差・貧困と社会保障制度の研究
四方 理人准教授
ヨーロッパ諸国では、この四半世紀の間に高齢者の貧困率が大きく低下した一方で、若者の貧困率が上昇し問題視されてきました。日本でも子どもの貧困が注目され、児童手当の拡充や子どもの医療費の無償化といった政策が実施されています。しかし、日本においては高齢者の貧困率が充分に改善しておらず、特に単身高齢女性の貧困率は40%を超えています。この背景には、女性の現役時代における就労期間の短さや低賃金があり、その結果として年金額が低水準にとどまるという課題があります。そこで、労働や家族などいろいろな側面から高齢者が貧困に陥らないためにどのような年金制度が望ましいのかを探求しています。また、医療・介護を含めた社会保障制度の役割に注目し、給付と負担の関係をいかにバランスさせるかを検討していますが、急激な制度改革は現実的ではないため、諸外国の政策を参照しながら、現行制度を踏まえた持続的で実効性のある選択肢を模索することを重視しています。貧困のない社会の実現に向け、社会保障制度の在り方について多角的な研究を進めています。
埼玉県『生活保護受給者チャレンジ支援事業』
生活保護受給者への支援と政策効果の検証
生活困窮者支援の取り組みの一つとして、埼玉県で『生活保護受給者チャレンジ支援事業』(通称:アスポート事業、「明日の港」を意味する)を実施しています。アスポート事業は、生活保護受給者に対する就労支援、地域での居住を促す住宅支援、そして貧困の再生産を防ぐ教育支援を柱としています。今日では全国で実施されている「生活困窮者自立支援制度」の原型ともいえる取り組みです。 本学を含む複数大学の研究者によって、アスポート事業の政策効果について調査・分析が行われてきました。実際に事業に携わる支援者や、支援を受ける当事者への聞き取り調査やアンケート調査を通じて、日本においてこれまで十分に把握されてこなかった生活保護受給者の実態や支援の成果が明らかになっています。これらの研究成果は、支援現場や行政にフィードバックされ、支援の改善や新たな施策の検討に活用。研究と実践が循環することで、生活困窮者支援の効果を高め、持続的な社会的包摂を実現することが目指されています。




