文学部 文化歴史学科
思想・芸術・文化・
地域・歴史から
人間の存在の本質を解き明かす
文化歴史学科の学び Study
専修紹介
哲学倫理学専修
哲学は、人間に関わるあらゆる事象について根本的な真理を理論的に極め、「人間とは何か、この世界でどう生きるべきか」を追究します。
美学芸術学専修
美術・工芸・音楽・演劇・映像、さらに現代アートなどの芸術作品を通して、「芸術とは何か」を歴史的、理論的に明らかにしていきます。
日本史学専修
歴史的観点から政治形態や法制度、地域社会構造、精神生活、祭祀など多様な研究に取り組み、日本や東アジアの姿を考察します。
アジア史学専修
固有の文化を持ちつつ互いに影響し合い発展してきたアジアの各地域が研究対象です。多面的視点でアジアへの理解を深めます。
西洋史学専修
ヨーロッパやアメリカを中心に西洋文明が影響を与えた地域の歴史を研究します。西洋史という視点から「世界」への理解を深めます。
文化歴史学科でできること
興味・関心に合わせて選択する6つの専修を設置
各専修における学修・研究を通して、人間の存在を思想、芸術、文化、地域、歴史という多様な視座から考察します。
専修の枠を越え多くの領域が学べる自由度の高い履修システムを採用
専修にとらわれず、関心に応じて幅広い分野の科目を自由に履修できる柔軟なカリキュラムを用意。自らの興味を深めながら、多角的な視点や思考力を養うことができます。
段階的に学びを深めることができ幅広い学識と深い洞察力を養う
基礎から応用へと段階的に学びを積み重ねることで、確かな知識と論理的思考力を育成。専門分野にとどまらず、幅広い視野を持って物事を考える力や、多様な価値観を理解する深い洞察力を養います。
4年間の流れ(美学芸術学専修)
美学芸術学基礎実習
この授業では、多様な芸術ジャンルの作品を鑑賞するための基礎的な知識を身につけます。講義のみならず、劇場、演奏会場、美術館の見学や、デッサン体験等を通じて、美学芸術学専修における各分野の基礎を学び、芸術の現場を体験します。たとえば 2025 年度は、住友生命いずみホールの舞台裏の機構や倉庫も含めた館内見学、関西学院大学博物館と西宮市大谷記念美術館では学芸員の仕事紹介や展示方法の現地学習、大阪松竹座での歌舞伎鑑賞をおこないました。

美学芸術学資料研究
2年次には、日本絵画、映像、西洋美術、日本工芸、西洋音楽、ポピュラー音楽のクラスに分かれて、各分野の基礎的研究手法を学ぶ「資料研究」を履修します。たとえば日本美術のクラスでは、代表的な日本の絵画について画像分析や古文書等の記録を読み解き、作品の見どころを掘り下げて学びます。映像のクラスでは、映像作品とシナリオ(脚本)の関係に注目した授業を行っており、2025年度は映画『石中先生行状記』(1950)を詳しく取り上げました。日本工芸のクラスでは、江戸時代の着物に関する資料の読解をとおして、くずし字の読解を習得します。
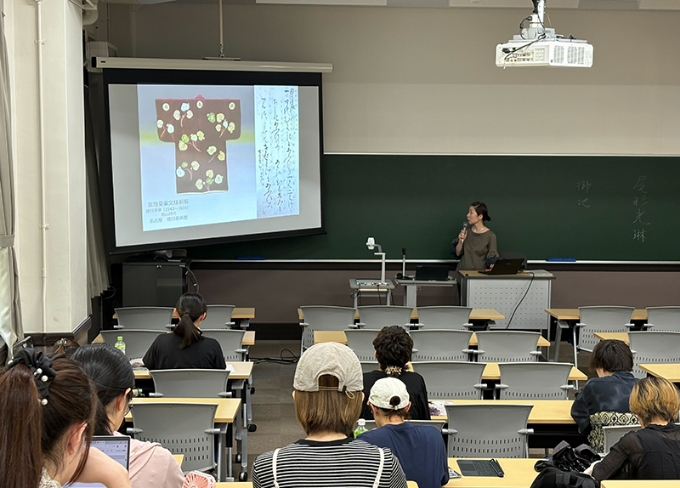
美学芸術学特殊講義
3年次になると、より専門に踏み込んだ「特殊講義」を履修します。特殊講義は各分野で開講されており、日本絵画では江戸時代の絵画について、特に狩野派、住吉派、琳派を詳しく取り上げます。映像分野ではフランス映画を分析するクラスもあります。西洋美術のクラスでは特に近代美術と科学や思想との関わりについて学び、日本工芸のクラスでは服飾史と染織史をたどります。音楽関連では、楽器の歴史を扱うクラスや、古典舞踏を実習するクラスを開講しています。これらの専門科目を履修したのちに、5つの分野のゼミでそれぞれの学生が卒業論文執筆に取り組みます。

卒業研究テーマ(抜粋)
- 道徳の情緒主義的解釈
- カントの「道徳的行為」について
- NHK「 みんなのうた 」 に見る 「 こどものうた 」 の変化
- ルーベンス《 戦争の災禍 》 における寓意・説話表現について
- 島根県知夫里島における定住対策事業〜 I ターン者 ・ 地域住民 ・ 行政の関係性に注目して〜
- 神戸市の2つの人工島はどのように変容したか─ ポートアイランド・六甲アイランドを事例として ─
- 律令制下の中宮職と皇后宮職
- 十五年戦争期における民衆動因と文化ついて
- トプカプ宮殿の庭園機能とボスタンジの職責 17 世紀初頭の外交使節 Ottaviano Bon の記述をもとに
- 宋代の大食商人の実態─ 中国国内と港市国家における活動から─
- ケルト人の他界観
- ローマ皇帝崇拝における皇帝と属州民との結びつき ─東方属州を中心に─
履修モデル
進路について Career
教育・文化分野への資格取得もサポート
文化歴史学科では、幅広い教養と専門性を活かし、多様な業界での活躍が可能です。また、中学校や高等学校の教員免許(社会、地理歴史、公民)に加え、学校図書館司書教諭や博物館学芸員などの資格取得が可能であり、教育や文化関連の分野への進路も開かれています。
社会につながる研究 For Society

フィールドワークを通して地域の現状を知る
山口 覚教授
地理学地域文化学専修ではエクスカーションⅠ(2年生)、Ⅱ(3年生)という授業科目で、野外実習(巡検、社会見学)をおこなっています。エクスカーションは2泊3日の日程で、毎年、国内のいずれかの場所において実施します。2024年以降の例では、福岡市北九州市、愛知県豊橋市、福井県福井市に宿泊地を設定しつつ、その都市とともに周辺地域を含めて巡りました。エクスカーションでは3日間の行程のうち、前半では大型バスや公共交通機関を利用して、教員が事前にセッティングした場所や機関を全員で訪問します。行政機関でまちづくりや産業の話を聞いたり、工場見学をしたり、その場所の景観を歩いて見て回るといったことをしています。後半では、学生はそれぞれ事前に計画したプランに従って、個別に現地調査を実施します。また、2年生はエクスカーションとセットで秋学期に地理学地域文化学実習Bを、3年生も同様に春学期に地理学地域文化学資料研究という授業科目を履修し、事前学習や調査内容の発表、レポート作成をおこないます。
福井県での現地調査
地域の文化と産業に触れる福井でのエクスカーション実習
福井県でのエクスカーションを例に、学生たちの現地での行動について記してみます。JR大阪駅で集合して列車で移動、越前たけふ駅から大型バスに乗って日本最大の漆器産地である鯖江市の「うるしの里」に参りました。そこで越前漆器協同組合の職員や漆器店の方から産地の状況を伺い、さらに徒歩で複数の店舗・工房をめぐりました。ここから越前市武生に移動して旧城下町を散策し、宿泊は福井駅前でした。翌日午前中には福井県庁を訪問し、産業労働部の職員の皆様から伝統工芸に対する支援体制の説明を受けました。これ以降は各自の調査となり、伝統工芸についてさらに深く学んだ者もいれば、各自治体の都市政策、農業や漁業、眼鏡製造業、食文化といった様々な関心に従ってそれぞれの対象地に赴き、聞き取り調査や資料収集をおこないました。




