
学生 損害保険業界に進み、 困っている誰かのための 安心できる存在になりたい。
神戸市出身。高校時代からの「誰かのために何かできる人になりたい」という思いをかなえるため、社会問題について広く学び解決方法を探る社会起業学科に進学。「人間福祉国内フィールドスタディ」での経験、ゼミや体育会サッカー部女子チームでの活動などを通じて、安心できる存在や居場所の重要性に気付く。卒業後は損保業界に身を置き、誰かのための安心できる存在になることを目指している。
実際のことはその場に行ってみなければ分からない。
「人間福祉国内フィールドスタディ」は大学2年生、3年生の2年間を通した授業で、興味がある社会課題について座学と実習で学びを深めます。私は在日外国人問題をテーマに3年生の春休み、アジア出身の「お母さん」たちが母国の家庭料理を提供する「神戸アジアン食堂バル SALA」で実習しました。店長の奥尚子さんは社会起業学科の卒業生で、1年生の時に受講した「多文化共生論」に講師として来られたのを機にSALAのソーシャルビジネスに興味を持ちました。90時間の実習では、ランチ営業で接客しながらお母さんたちとコミュニケーションを取る中で、日本語が分からず電車にも乗れなかったこと、奥さんと出会ってようやく居場所ができ、ありのままの自分を出せるようになったことなどを聞きました。
奥さんと話して印象的だったのは、「たとえ共感できなくても、まずは理解すること」という言葉です。育ってきた環境が異なると、その人が大切にしている価値観も違います。自分と異なる部分があったとしても、その人の国・地域の文化や価値観、育ってきた環境や背景を理解し、考えを尊重する姿勢が大切だと思いました。これからも、その姿勢を持ち続け、多様な人と関わる中で視野をもっと広げていきたいと思います。
実習後の実践報告会では、居場所の大切さ、互いを理解する大切さとともに、行ってみなければ分からないということを発表しました。SALAは、在日外国人の居場所としてきらきらしたイメージですが、実際にはたくさんの苦労があり、それらを乗り越えて現在があることは、その場に行って初めて感じられるものだと思います。

「ゼミ生全員で作り上げた」と言えるイベントに。
スポーツ経営学やスポーツマーケティングを研究分野とする林直也教授のゼミに所属し、スポーツと社会問題を掛け合わせたイベントに取り組んでいます。学生ならではのユニークな発想のイベントに私もトライしたいと思ったのがきっかけです。3年生の夏には、関西独立リーグに所属する野球チームの集客イベント「あなたの心を“カッサ”らう!YourselFurugiでファッション勝(show)!」を実施しました。廃棄傘や放置傘、ファストファッションの流行による不用衣類などに着目し、ごみを他のものに変身させるというテーマで傘の骨や古着を使ったミニ応援旗をファンに配ったり、古着をつなぎ合わせて作成した大きな横断幕にメッセージを書いてもらったり、古着でファッションショーをしました。夏休み中、みんな慣れない裁縫で手に針を刺しながら頑張りました。今年の春には小学3年生を対象にした授業で、サッカーや玉入れ、劇などを通じてごみの分別の大切さを楽しみながら学んでもらう「これなにゴミ?!目指せ分別マスター!」を行いました。とても評判が良く、4年生になった児童たちに今秋、再び出前授業を行う予定です。
テーマ決めに始まり、グループに分かれての企画書作成、内容の検討、グッズ作りなど、イベントの準備にはゼミ生全員で取り組みます。林教授は、客観的な視点からの軌道修正やアドバイス、当日は記録係としてカメラマンに徹するなど、私たちがやりたいことを全力でサポートしてくださいます。私は3年生からゼミ長をしており、「みんなで作り上げた」と胸を張って言えるよう、全員が役割を分担することを意識しており、また、一人一人が自分の思っていること、やりたいことなどを発言しやすい雰囲気づくりにも努めています。

誰かのために行動を起こせる人になりたい。
社会起業学科は、「多文化共生論」をはじめ、1年生春学期の「人間多様性論」「社会起業フィールドワーク」、3年秋学期の「ディアスポラ論」など、ゲストスピーカーの話を聞いたり、グループワークで他の学生の意見に触れたりといった授業が多いのが魅力です。
ゲストスピーカーによる授業では、その人がどんな思いで会社を立ち上げ、周りにどのような影響を与えているのかなど、人生観や生き方を学ぶことができます。特に印象深かったのは、男性として生まれたけれども心は女性で、性別適合手術を受けられた方のお話です。そのような人に出会うのも、話を聞くのも初めてで、まだまだ偏見の残る日本でカミングアウトして起業し、たくさんのLGBTQの人たちの安心できる居場所となっていることを知りました。人のため、社会のためにと行動を起こした人たちの志や行動は勉強になりますし、私も誰かのためにそういう行動を起こせる人になりたいと大いに刺激を受けています。また、私は人と話すことが好きなので、みんなで意見を出し合って一つのものを作っていくグループワークは大好きな学びの時間です。知らなかった価値観や思いもよらなかった発想に驚かされるのも楽しいです。
社会起業学科では学生の興味ややりたいことを尊重し、それに対し先生方が親身に寄り添ってくださいます。また、興味のある分野に実際に足を運べる機会も多くあります。漠然と社会問題に興味があっただけの私のような者も、貧困やジェンダー、教育格差などさまざまな社会問題を幅広く学ぶ中でたくさんの気づきを得られました。
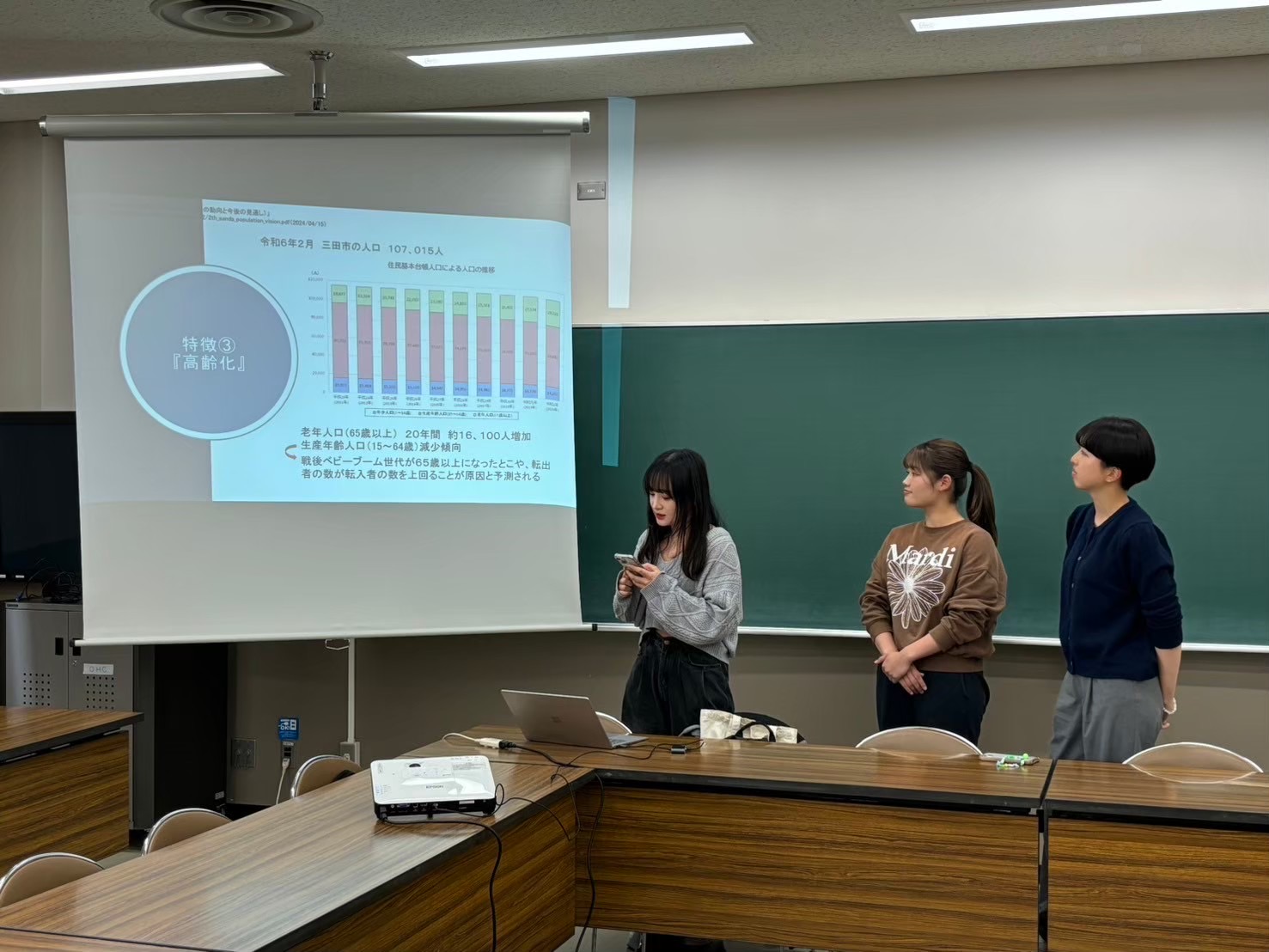
苦しい時にもう一歩頑張ろうと思える力がついた。
中学、高校とサッカー部でしたが、大学の体育会はレベルが高く入部する勇気が出ませんでした。でも、心のどこかでずっと「サッカーがやりたい」「人として成長したい」という気持ちがありました。このまま大学生活を終わってしまったら絶対に後悔すると思い、2年生の6月末に入部を決めました。入ってすぐの3部練合宿では、体力が追い付かない私はみんなの背中をずっと追いかけていました。とにかく合宿をやり切りたいという思いで挑んでいましたが、坂道を走るトレーニングでは周回遅れになり心が折れそうになっていました。すると、当時4年生の先輩が横に付いて一緒に1周分余分に走ってくださったのです。その優しさに触れたのに加え、しんどい時こそ鼓舞し合い、高め合っているみんなの姿を見て、私もこの先チームやチームメイトのために頑張ろうと決意しました。
プレー面では、ずっと挑戦し続けることを心がけています。ポジションはゴールキーパーで、入部当初は同期に2人いて、私は3人目です。実力差は簡単には埋まらず、試合に出られないことも多いですが、レギュラーの代わりにピッチに立った時には、みんなを安心させられるようなゴールキーパーを目指しています。もちろん悔しい気持ちもありますが、それでも入ってよかったと思えるのは周りの仲間たちのおかげだと思います。優しくて、相手を思いやれる人ばかりです。また、部活動を通じて、自分としっかり向き合えるようになりましたし、しんどい時にもう一歩頑張ろうと思える力がついたとも感じています。
プレー外では、チームの動画を撮影してSNSで発信する係をしており、それらの技術は、ゼミでもインスタグラム係として広報活動に生かすことができています。

就職活動で安心できる存在や居場所の大切さに気づく。
就職活動を始めるまで、自分が将来何をしたいのかがはっきりしませんでしたが、自己分析を進める中で、徐々に明確になっていきました。これまで私がいろいろなことに挑戦し続けられたのは、寄り添ってくれる家族や部活動の仲間、大切な友達といった安心できる存在がいて、安心できる居場所があったからです。それは、人が頑張るための原動力となるものだと実感しました。だから、今度は私が誰かのための安心できる存在、居場所になりたい、そして「誰かのために何かしたい」という高校生の時からの思いをかなえたいと考え、損害保険業界への就職を決めました。
かなうならば、事故に遭われた方に対応する損害サポート部門に所属して、困っている人、一歩前へ踏み出そうとしている人に寄り添い、支え、挑戦を後押しすることが希望です。それぞれ抱えているものは違い、悩んでいることも異なりますが、それらをきちんと聞いて理解し、解決へ導ける人でありたいと思っています。大学4年間、社会起業学科でさまざまな人と出会い、話し、多様な価値観があることを学びました。その蓄積を基に、グループワークなどで培ってきたコミュニケーション力、受容する心を生かしながら、一人一人に寄り添える人でありたいと考えています。


