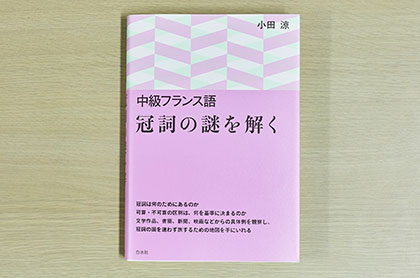研究者 フランス語の深遠が導く「新たな世界観」
ネイティブにも難しいテーマ、だからこそ挑戦
私の主な研究テーマはフランス語や英語の冠詞です。日本語にはない冠詞は、日本語を母語とする学習者には正しく使いこなすのがとても難しく、「冠詞は、どれだけ英語やフランス語がうまくなっても、最後まで間違いが残りがち」と言われるほどです。しかもフランス語には、英語にはない部分冠詞というものまであります。文を書いたり話したりするときに迷うことなく冠詞を使い分けているネイティブ・スピーカーに「なぜこの場合は定冠詞(不定冠詞)なのか」と尋ねても、その理由をいつもうまく説明できるわけではありません。ネイティブにとっても論理的な説明をすることが難しいからこそ、言語学者が研究する意味があると思っています。

映画・小説・論文・・・すべてを学びの題材に
ゼミでは冠詞だけでなく、代名詞や接続詞、前置詞、動詞の時制など、フランス語学の様々な問題について考えます。狭い意味での文法の枠を超えて、発話者が対象や出来事をどのように捉えているのかなどについて皆で議論します。例えば、実際の言語使用の場を観察するために、フランス映画のスクリプト(台本)を配布し、ナレーションやセリフのフランス語を分析して発表してもらっています。映画ならフランス文化も同時に学べますし、字幕の誤訳を見つけるのも面白いものです。フランス語学の分野の研究論文を読み、論文を執筆するための基本的な方法論を学ぶことも大切です。同時に、映画の字幕や小説の翻訳が常に正しいとは限らないこと、また文法書や研究論文に書かれていることがすべて正しいとは限らないことに注意するよう指導しています。

日本の「当たり前」を広い視野で問い直す
言語学としてフランス語を学び研究することは、フランス語の運用能力を高めることにつながります。異なる文化の人と直接コミュニケーションできるようになり、フランス語で発信されたメディアの情報にもアクセスできます。フランス語に限らず、外国語を習得できれば、得られる情報の種類は多くなり、幅広い視野を持つことができるでしょう。世界の出来事の捉え方についても、フランスは必ずしも日本と同じではありません。日本に暮らす私たちが「当たり前」だと思っていることは、フランスでは、世界では、そうではないのかもしれない。フランス語を学び習得することで、私たちは新たな観点から世界を見ることができるようになるのです。

外国語を知る 人間を知る 自分を知る
フランス語や英語などの外国語は、コミュニケーションの手段・道具として有効です。でも、私は、目的があって外国語を学ぶのではなく、外国語を学ぶことそれ自体が目的であっても良いと思うのです。言語について考えることは、「人間は世界をどのように捉えているのか」について考えることです。ゲーテの言葉に「外国語を知らない者は、自分の言葉についても無知である」とあるように、自分の母語を見つめ直すことでもあります。知識は人格を形成し、人間を育てるものです。外国語の学習に限らず、大学での学びには、「何かの役に立つ」という理由は必ずしも必要ではなく、純粋に自分の知的好奇心を追求するものであって良いと思っています。

第2外国語だったフランス語、気づけば学究の徒に
もともとは文学が好きで、大学では日本文学を研究しようと思っていました。日本語学や言語学の授業を受けているうちに言葉の研究が面白くなってきて、第2外国語に選択したフランス語の勉強も楽しかったので、フランス語学を研究することにしました。博士論文をもとに書いた『認知と指示 定冠詞の意味論』で、渋沢・クローデル賞(※1)を受賞したときは本当に驚きました。文学や芸術、社会学の研究に贈られることがほとんどで、理論的な言語学の分野では初めての受賞でしたから。通知が来たときも、はじめはスパムメールではないかと思ったぐらいです(笑)。本当に励まされ、「初心忘るべからず」という気持ちで、受賞盾を研究室に飾っています。
※1 日仏両国において、それぞれ相手国の文化に関してなされたすぐれた研究成果に対して贈られる学術賞。

「もしかして外国に住んでおられましたか」
大学の1・2回生の頃は、フランス語の先生に「あなたのフランス語は英語なまりですね」と言われていました。それが3・4回生になると、英語の先生に「あなたの英語はフランス語なまりですよ」と言われるようになり、少し前にイタリア語の学校に通っていたときには、イタリア人の先生に「なんだかフランス語っぽいイタリア語だね」と言われました。揚げ句の果てには、日本のあるお店で「もしかして外国に住んでおられましたか。シの発音が外国語っぽい発音ですよね」と言われてしまいました。どうやら今では、日本語すらフランス語なまりになってきているようです。悲しむべきか、フランス語の研究者としては本望と言うべきか(笑)。

初夏にはバラの花、心落ち着く文学部の中庭
日本建築学会賞(※2)受賞のキャンパスはどこも美しく、なかでも私が気に入っているのは文学部の中庭です。初夏にバラが咲いて、すごくきれいなんですよ。近くで授業があるときには必ずそこを通ります。私にとってとても落ち着ける場所です。晴れやかで、自由に研究できる雰囲気がある関学は、学生も明るいですね。スクール・モットーが「Mastery for Service(奉仕のための練達)」だけあって、ボランティア活動に参加している学生もとても多いように感じます。「社会の役に立ちたい、誰かを助けたい」と思う気持ちは、とても大切だと思います。関学では全学部の学生向けに日本手話の講座も開講されていて、私も1年前から勉強しているんです。
※2 関西学院西宮上ケ原キャンパスは、1929年の創建以来の設計思想を継承しながら、現在の大学に求められる施設の機能向上を的確に行ったことが評価され、2017年に一般社団法人日本建築学会より日本建築学会賞(業績)を受賞しました。

「月を目指せ もし外しても星には行ける」
趣味は小説を読むことや映画鑑賞で、最近見たなかでは、アカデミー賞を受賞した『ローマ』に感動しました。絵画や彫刻も好きで、特に今興味があるのはアフリカの美術。コートジボワールのダン族やヤウレ族の仮面を購入し、いくつかは研究室にも飾っています。研究分野ではこの4月、一つの区切りとなる著作『中級フランス語 冠詞の謎を解く』を出せました。とは言え、まだまだ追求しなければならない問題はたくさんあります。「月を目指せ もし外しても星には行ける」。この言葉を胸に、目標を高く持って研究を続けてゆきたいと思っています。私の専門外のテーマを研究しているゼミ生たちも多く、指導しながら一緒に勉強できることも、いい刺激になっています。