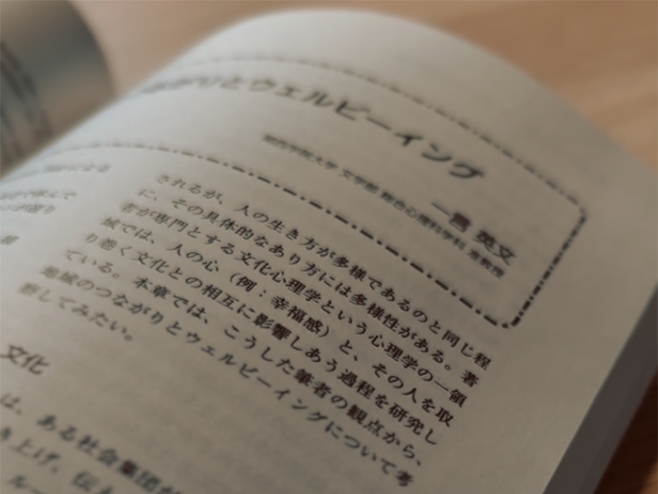文学部
総合心理
科学科
複雑な人間の心を探り、
行動のメカニズムを
解明する
総合心理科学科の学び Study
専修紹介
心理科学専修
人間を科学的観点からとらえ理解することをめざし、人間の心理的諸相について認知・行動・発達の在り方や病理を含めて探究します。
総合心理科学科でできること
早期から実習を通して、実践力と専門性を養う
1・2年次から実習が必修となっており、心理学の基本的な技法や姿勢を早い段階から身につけます。段階的に知識と経験を積み重ねることで、実践力と専門性を高めます。
心理科学実践センターで、国家資格「公認心理師」に対応した学びを提供
本学が長年培ってきた科学的心理学を基礎とした心理臨床の実践を行う臨床・研究・教育施設「心理科学実践センター」。ここでの学びを通して知識を現場で活かす力を育てます。
充実した実験設備で実践的に学ぶ
4年間の流れ
人文演習Ⅱ
1年生を対象とした演習授業で、専修ごとに別れて実施されます。総合心理科学科では、班に分かれて心理学に関する書籍や論文にあたり、その内容を丁寧に読み解いて、クラス内で発表と議論を行います。授業を通じて心理学の多様な研究テーマに触れることで関心の幅を広げるとともに、学術的な情報を主体的に収集・整理する力、他者にわかりやすく伝えるプレゼンテーション能力、建設的な議論を通して理解を深める姿勢を養うことを目指します。

心理科学実験実習Ⅰ、Ⅱ
「こころ」は身近な存在でありながら、その本質を科学的に捉えることは容易ではありません。心理科学実験実習では、心理学の基本的な研究手法である行動実験を通じて、「こころ」を科学的に理解する方法を学びます。様々なテーマを題材に、実験の計画・実施・データの統計分析・レポート作成までを一貫して行い、心理学の研究に必要なスキルを基礎から身につけていきます。授業は25人程度の少人数で行われ、担当教員に加え、大学院生と学部生のアシスタントが学習を丁寧にサポートします。実践的な学びを通じて、心理学の面白さと奥深さを体感できる授業です。

心理科学研究実習
総合心理科学科では3年生からゼミ(演習)に所属し、より専門的な心理学の研究分野について学んでいきます。学術論文の輪読や卒業論文の作成に向けた指導はゼミで行われますが、より具体的な研究手法(実験、調査、検査、観察等)を習得するために3年次においては心理科学研究実習と呼ばれるゼミごとに実習形式で研究に取り組む機会を設けています。この授業は「ゼミ別実習」とも呼ばれており、各研究室・ゼミで特色のある研究手法について実践形式で学ぶことになります。この心理科学研究実習を経て、4年次において卒業論文の作成に本格的に取り組んでいくことになります。

卒業研究テーマ(抜粋)
- 1〜2歳児の愛着と共感性の関連についての実証的研究〜共感的行動を指標として〜
- ラットにおける同情による向社会的行動
- ソーシャルメディアにおける自己開示と主観的幸福感の関係
- 写真を撮ると記憶が良くなる?─順行干渉低下による学習の促進
- 思考制御能力の高い人はよく忘れられるか?─指示忘却と思考制御能力の関連
- 記憶の制御抑制機能と精神的健康の関連
- じゃんけん課題における同調的な行動は個人空間距離を縮めるのか?
- 赤ちゃんから子どもへ変化していく時期の心理学研究の傾向
- 2種類のパズルゲーム課題が脳波・自律系指標に与える影響の検討
進路について Career
「公認心理師」の資格取得を目指せる
総合心理学科では、公認心理師の資格取得を目指すことができ、専門的な知識と実践力を身につけながら、将来の進路の幅を大きく広げることができます。医療・福祉・教育・企業など、さまざまな分野で活躍できる力を養います。
※公認心理師の受験資格取得に必要な科目の一部は履修者人数の制限を設けており、GPA(Grade Point Average)による選抜があります。従って、希望者全員がこれらの科目を履修できるとは限りません。
社会につながる研究 For Society

「協調的幸福感」の文化的多様性を読み解く
一言 英文教授
私の専門は比較文化心理学です。特に、幸福感の文化差について実証的な研究を行っています。幸福感は、一見個人的なものに思われがちですが、人々が暮らす社会やその歴史、果ては自然が織りなす文化によって、何を幸せと感じるか、という意味づけには系統的な違いが生じています。この点、伝統的な心理学の幸福感研究では、個人的に理想とする何かを獲得することを幸せの意味づけとして注目してきたきらいがあるのですが、東アジアや稲作地域で見られる対人関係の調和や平穏を主な意味づけとする幸福感の存在や働きについては未だ明らかになっていないことが多い現状です。私の研究では後者の様な幸福感を「協調的幸福感」と名付け、その個人差や健康との関わり、地域社会の維持との関わりについて、国際比較や地域比較調査を用いて実証的な測定に基づいた研究を行っています。
関西の各自治体との連携
文化に根ざした心の計測と地域政策への応用
4半世紀後、世界人口の7割が都市部に住むと予測され、特に東京一極集中による社会的コストが課題の日本は、地域に人を繋ぐ手段が求められます。この中で、エビデンスのある政策提言に貢献するため、協調的幸福感の測定を企業や地域と連携して行っています。例えば、関西はT市の研究機関と連携し、協調的幸福感と定住意向(この町に住みつづけたいと思う意識)とに比例関係を見つけ、機関誌にこの知見を還元しました。経済財政運営と改革の基本方針―骨太の方針―(内閣府, 2023)にもあるように、地域基本計画のキー・パフォーマンス・インジケーターにこうした心理指標を用いることで、文化に培われた心と現代の社会問題に実証的な楔が打てると考えています。