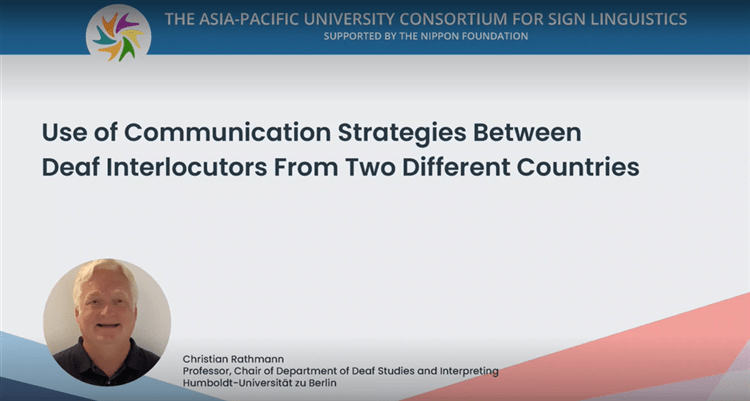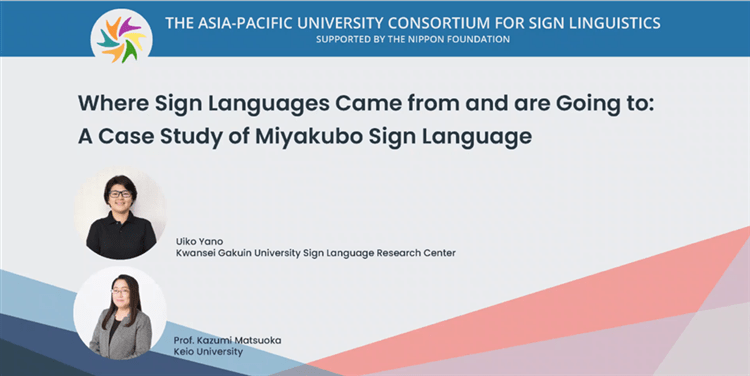海外大学との手話言語学、ろう文化等に関する共同研究の講演動画:第4回・第5回を配信しました
手話言語研究センターは、手話を研究している
海外の5大学※
と共同で、手話言語学、ろう文化、ろう研究等に関する全5回の講演動画を配信します。
今回は第4回・第5回の動画を公開しました。
| 講師 | 講演タイトル | |
| 第1回 | Thomas K. Holcomb 教授 (Professor, Deaf Studies Division, Ohlone College) |
To Be or Not to Be Deaf : That is the Question (ろう者であるべきか、そうでないべきか) |
| 第2回 | Jemina Napier 教授 (Chair of Intercultural Communication in the Department of Language & Intercultural Studies, Heriot-Watt University) (Director, The Centre for Translation & Interpreting Studies in Scotland) |
An overview of the transformation of Sign Language Interpreting as profession & research, & SLIS as a transformative field (職業、研究における手話通訳の変革と変革の場としての手話通訳学) |
| 第3回 | Cathy Easte 氏 (Manager, Student Disability and Accessibility Student Success, Griffith University) Riona Tindal 博士 (Senior Disability Advisor, Student Disability and Accessibility Student Success, Griffith University) |
Student Disability and Accessibility (障害学生とアクセシビリティ) |
| 第4回 | Christian Rathmann 教授 (Chair of Department of Deaf Studies and Interpreting, Humboldt-Universität zu Berlin) |
※第4回は日本語字幕のみ。日本手話翻訳動画は近日公開予定です。 |
| 第5回 | 松岡 和美 教授 (慶應義塾大学 教授) 矢野 羽衣子 氏 (関西学院大学 手話言語研究センター 客員研究員) |
Where Sign Languages Came from and are Going to: A Case Study of Miyakubo Sign Language (手話言語はどこから来てどこへ行くのか:宮窪手話の研究) |
- 第4回 概要・講師紹介 第4回目の講演タイトルは”Use of Communication Strategies between Deaf Interlocutors from two Different Countries“(異国のろう者同士のコミュニケーション戦略使用について)です。
講師はベルリン・フンボルト大学教授のChristian Rathmann氏です。
前半は、「2つの異なる国のろう者同士のコミュニケーション方略」と題し、ご自身の経験を語っていただきます。後半は、「国際手話:ろうの手話使用者が共有する非ローカル言語」と題し、Ronice Muller de Quadros氏との共同研究をご紹介いただきます。日本語訳を表示させるためには、画面右下の「CC」ボタン(キャプション表示)を押して下さい。

Christian Rathmann 教授
ベルリン・フンボルト大学教授。彼の指揮のもと、ろう者学(学士)および手話通訳学(修士)プログラムが実施されている。
現在、言語の標準化、国際手話、第二言語習得など、数多くの研究に携わっている。
また、ろう児の早期教育、教育政策などにも取り組んでいる。
第5回 概要・講師紹介
第5回目は、日本からの講演です。タイトルは" Where Sign Languages Came from and are Going to: A Case Study of Miyakubo Sign Language″(手話言語はどこから来てどこへ行くのか:宮窪手話の研究)です。
講師は松岡 和美 教授(慶應義塾大学)と矢野 羽衣子 氏(関西学院大学 手話言語研究センター客員研究員)です。ご自身が研究されている地域共有手話である宮窪手話についてのお話を中心に、地域共有手話の特徴や研究の重要性にもふれてお話しいただきました。また、ろう者自身が研究を行うことの重要性や聴研究者がろう者と協働で研究を行うことについてもお話しいただいています。

松岡 和美 教授
慶応義塾大学教授(英語)。コネチカット大学大学院言語学部博士課程修了(Ph.D.)。日本手話の統語論およびろう児の言語発達を専門とする他、ろう者と共同し、日本手話の意味論・類型論・音韻論・M2L2習得の研究にも携わる。著書に『日本手話で学ぶ手話言語学の基礎』(くろしお出版、2015年)、『わくわく!納得!手話トーク』(くろしお出版、2021年)などがある。NHK Eテレ「みんなの手話」監修(2018年~2019年)、オンライン手話学習サイト「アイオー」監修。

矢野 羽衣子 氏
関西学院大学手話言語研究センター客員研究員。国立大学法人筑波技術大学大学院技術科学研究科情報アクセシビリティ専攻修士課程修了。出身である愛媛県大島で使われている「宮窪手話」をきっかけに、共有手話に関する研究に着手するほか、不就学のろう者や離島に住むろう者の手話コーパス構築に関する研究も行なっている。